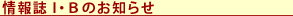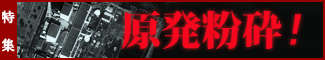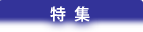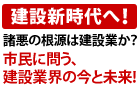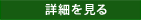特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
今、歴史から元気をもらおう
安政5年(1858)7月6日、第13代将軍徳川家定が病死した。その喪が発表されたのは8月8日である。正室の篤姫はついに臨終の場に立ち会えなかった。病弱で早くから隠遁が工作されていた家定の孤独と無念を思い篤姫はひとり涙する。二十四才の若さで髪を下ろした彼女は天璋院と号することになった。10日後の16日には、篤姫の養父である島津斉彬が49才の若さで突然亡くなった。篤姫が将軍家に嫁ぐことになったのはそもそも斉彬の意向である。紀州家の慶福(よしとみ)が14代を継いで将軍家茂(いえもち)に就任する。僅か十三歳の幼い将軍だった。
万延元年(1860)3月2日、「安政の大獄」を強行した井伊直弼が桜田門外で暗殺されると、ただでさえ傾きかけていた幕府の威信はさらに地に落ちた。この事態を打開しようと幕府は公武合体の方策を打ち出した。公は朝廷であり武は幕府である。朝廷との絆を深めながら湧き上がる尊王攘夷論を幕府自体が取り込んでしまおうとしたのである。朝廷と幕府の和解のための象徴として臣籍降嫁が目論まれた。候補者となったのが孝明天皇の妹君・和宮である。和宮にはすでに有栖川熾仁(たるひと)親王という許婚がいた。「絶対に江戸には嫁かない」という和宮だったが、最後は「すべては天下安寧のためだ」という兄君の言葉がすべてを決めた。
和宮が江戸に到着して大奥に入ったのは文久2年(1862)の2月だった。御台所空席の大奥を仕切っていた天璋院に対して、和宮付きの女官たちは、万事に京都御所風暮らし方を主張した。天璋院は万事に武家の流儀に従へと命じた。和宮は御台所となることを拒否した。二人の対立について勝海舟は次のように語っている。「二人の仲が悪いのは、お付のせいだ。和宮が初めてのときお土産の包み紙に『天璋院へ』とあったのは、いくら上様でも徳川に入った以上は姑だから書き捨ての法はないと、お付が怒ったそうだ。一事が万事そういう具合よ。(氷川清話)」
慶応元年(1865)5月、「第二次長州征伐」が始まった。幕府は征長のため将軍みずから軍を率いて進発すると布告した。家茂は、神君徳川家康が関ヶ原に進発したときの例にならって、金扇と銀三日月の馬印を立てて威風堂々の軍を進めた。だがこの出発は若き将軍の帰らぬ旅路の第一歩となった。長州征伐は進まず、家茂は大坂城に在陣し続ける最中の慶応2年(1866)7月20日家茂が突然没した。脚気衝心との見立てであった。あまりにも急な死に将軍毒殺との噂がとびかった。前将軍家定の死因も脚気と診断されている。大奥にある天璋院は二度にわたる常ならざる死に対する不審の思いを禁じることができなかった。
昭徳院とおくり名された家茂の遺骸が芝増上寺に葬られたのは9月23日である。髪をおろした和宮には天皇から静寛院宮という院号を賜った。ところが悲劇はさらに続く。12月25日には兄君の孝明天皇が崩御されたのである。こうして公武合体の象徴として降嫁した和宮は、ただひとり江戸城に取り残された。このとき静寛院に手を差し伸べたのが天璋院である。相次いで近親を亡くした者同士の相寄る魂でもあった。「これからの大奥は私と宮で統べて行く」という天璋院の言葉は静寛院へのなによりの励ましとなったにちがいない。
二人に共通していたのは徳川慶喜への反感である。天璋院は、以前から慶喜に野心ありとみて陰謀の影を感じていたし、和宮は兄の意を受けて攘夷を求める督促状を慶喜に送っていたが、ことごとく無視されたことに不快感をもっていた。鳥羽伏見の戦いで、戦局利あらずとみるや、さっさと江戸に帰った慶喜は、とるものもとりあえず天璋院に面会を求め、「朝敵の称のご赦免を静寛院を通じて朝廷にとりなし願いたい」と深々と頭を下げた。過去のいきさつはぬぐいがたいものがあったが、「朝敵の汚名を蒙った上は徳川家の存続も危うい。十五代も続いた徳川家の断絶の憂き目を見るには忍びない」という点で静寛院とも意見を合わせた。島津家出身の天璋院篤姫と皇族の静寛院和宮である。二人とも自分の実家と徳川家が戦うことは絶対に避けたいとの思いであった。
この時期、慶喜に向かって恭順を説いたのが勝海舟である。内戦を避けるには慶喜の恭順が絶対条件だった。勝の脳裏には天璋院と静寛院のお姿が浮かんでいた。しばらくして天璋院と慶喜が静寛院の御殿を訪ねた。天璋院は自分とともに静寛院を上座に座らせ慶喜を下座に着かせた。慶喜は、自分か心底から天皇を尊崇しており和平を望んでいることを述べた。天璋院がすでに結論を出していることを知った静寛院は「何ぞ、力になろう」と声をかけた。その後静寛院は慶喜の赦免を求める使者を京都に送った。この行動をきっかけとして、勝は和平を求め本格的に動き出していく。
小宮 徹/公認会計士
(株)オリオン会計社 http://www.orionnet.jp/