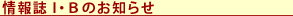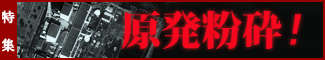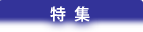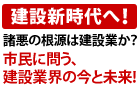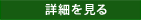特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
経済小説
第7章 中央集権(3)
とうとう誰も本音を言わない、言えない雰囲気の会社になってしまった。
坂本社長から「お客さんに礼を尽くせ」「風通しを良くせよ」等の訓示があっても、社員の共感を呼ぶどころか、「あんたはどうなの」という、声なき声やしらけたムードが広がるばかりだった。
社員の士気は落ちていくばかりであった。
こうした社内の雰囲気は坂本には正確に伝わっておらず、坂本の過信はますますひどくなり、高慢さは増すばかりだった。権力志向の強い坂本を指名した中井の責任は大きい。しかも、坂本の社長就任前に、これほど芳しくない坂本の風評批判を知っていて、いくらでも、人事上の決定をくつがえすことができたはずなのに、しなかったことの罪は大きい。
坂本が社長候補となって以来、中井のもとには坂本の黒い噂に関する投書が殺到していた。中井は密かに先輩・部下からも、「坂本だけはやめた方がいいですよ。名古屋はひどい状況でしたよ」とアドバイスを受けていた。坂本の名古屋時代の専制君主のような振る舞いを知っている人たちからのアドバイスだった。
しかし中井は、折角のアドバイスを真剣に聞いてはいなかった。
中井は坂本が自分にたてつくことすら想定していなかったのである。
中井は自らが渡部との間で、会社を会長派と社長派に二分する戦いを経験したことを忘れていた。現役の社長が持つ実権の強さを自らが体現し、渡部との戦いに勝利したことを忘れていたのだ。しかも、中井は人を疑わない性善説の人であった。
創業者の山田や中井のように、山水工業グループの王道を歩いてきた人にとっては、今日のような状況が出来するなどということは、想定外であったろう。
案のじょう、権力を握った坂本は、すべての権限を自分に集中させ、名古屋時代と同様に、専制君主のような存在となってしまった。
しかも、自分を社長に指名した中井ですら、自分のゆくてを邪魔する者として、排除しようとしているのだ。
権謀術数に長けた坂本は、社長という立場を最大限に使い始めた。
「飼い主が飼い犬に咬まれる」事態となってきた。
(この物語はフィクションであり、事実に基づくものではありません)