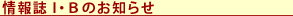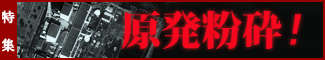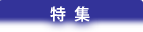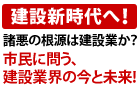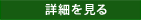特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
特別取材
もはや経済ニュースの指定席を確保したかに見えるファーストリテイリング(FR)。昨年秋の世界同時不況以降、日本経済は完全に失速。それを嘲笑うかのように、同社は好調な業績をあげている。その理由は何かと言えば、商品を生むマーチャンダイジング(商品政策)に尽きる。商品づくり=メーカーという意識が強い日本で、FRという小売業はその仕組みを完全に変えた。専門店はもとより、百貨店も総合スーパーも凌駕するFRの商品力は、はたして本物なのだろうか。
1.いち早く欧米の製造小売業を手本に
ファーストリテイリングは1984年、広島に「ユニーク・クロージング・ウエアハウス」をオープンした。翌85年から展開した郊外店が当たり、「カジュアルは年齢や性別に関係なく、ベーシックなデザインなら売れる」と判断。当初は国内のメーカーから仕入れて売っていたが、店舗数が増えるにつれて計画的な商品調達が必要になり、87年からオリジナル商品、いわゆるPB(プライベートブランド)の開発に着手した。
これが今日のユニクロを象徴する「商品づくり」の起源と言える。モデルにしたのは当時、欧米で人気のあったギャップやネクストといったSPA(製造小売業)。これらの企業は商品企画から販売までを一貫して行ない、在庫リスクも自社で負いながら、顧客満足も徹底して追求し、最大の利益を上げていた。
しかし当時の日本では、小売業はメーカーの商品を仕入れて売るだけで、残れば平気で返品する。メーカーは返品リスクを原価に乗せた商品しか作らない。結局、消費者がそのツケを払わされるばかり。欧米のSPAシステムは、それほど画期的なものだった。
日本の小売業ではどこも手をつけていなかったこのビジネスモデルに、地方の一専門店チェーンが挑む。無謀とも言えるチャレンジだったが、組織が小さく硬直もしていなかったからこそ、地道なシステムづくりは可能となったのである。
最低価格で誰もが着られる服
しかし、欧米型のシステムをそのまま日本に持ってきても、“うるさい消費者”を納得させられるような商品は生み出せない。それは親の代から専門店を経営し、日頃からお客に接してきた柳井正社長がいちばん良く分かっていた。
そこで柳井社長が考えたのが、「高くて良い服」と「安くて悪い服」しか存在しない日本の衣料品市場において、「安くて良い服」=「老若男女誰にでも合う、しっかりした最低価格の普段着(カジュアルウエア)」を提案することだった。
ただ、多店舗化が進んだ90年代前半、ユニクロの商品は、価格は安かったものの、ファッションアイテムとしてはとても褒められたものではなかった。こうした商品力が払拭されたのが98年秋の「東京・原宿」への進出と「フリース」のブレイクである。
最低価格に品質が伴い、カジュアルのスタイリングが決められ、商品の絞り込みも提示された。今日の原動力でもある商品政策のコンセプトが固まったのである。そして、こうした商品づくりを具現化したのが、海外工場への生産委託と生産管理技術である。
当初、FRは原材料の調達や海外生産ノウハウをもっていなかった。そこで総合商社の三菱商事と組み、そのさまざまなビジネス機能を利用。それにより、海外でのビジネスコーディネートや物流システムの整備、原材料調達が容易となった。
【剱 英雄】
*記事へのご意見はこちら