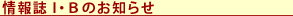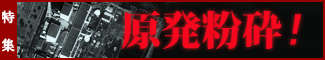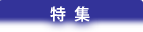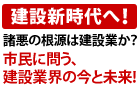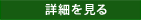特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
社会
今月17日、鹿児島県薩摩川内市で行われた、鹿児島大学理学部・佐藤正典氏らの講演会を取材した。「生物学から見た原子力発電所の環境問題」~原発は、海を温暖化し、魚介類の子どもを殺す~と題した佐藤氏の話は、事故による放射能汚染の怖さのほか、主として原発の「温排水」が自然界にもたらす影響についてだった。概略をまとめてみた。
原子力発電所では、電力が作られる過程で、タービンを回すために発生した蒸気を冷却する際、大量に海水を取水する。当然、排出される海水は蒸気の熱で温度が上昇しており、この温まった海水を「温排水」という。そのため、発電所は海岸付近に建設される。
この「温排水」には、いくつかの疑問が提起される。
第一の問題は、暖められて放水された「温排水」による海水温の上昇だ。取水口付近と排水口付近の海水の温度差は、安全協定で上限を7度と定められている。安全協定が守られているとしても、7度も高い温排水は、それだけで周辺海域に変化をもたらす。
 佐藤氏とともに講演を行った地元出版社の代表・向原祥隆氏の話によれば、川内原発では、周辺海域の調査などから、放水された海水が再び取水口から取り込まれ循環している疑いが強くなっているという。いったん暖められた海水が、十分冷やされることなく、さらに加熱されると、海水温の上昇は加速していく。水温が高い海水が拡散すれば、環境に大きな変化をもたらすのは自明の理である。そこで生息する生き物にも多大な影響を与える。海の資源が枯渇する可能性さえはらんでいるという。
佐藤氏とともに講演を行った地元出版社の代表・向原祥隆氏の話によれば、川内原発では、周辺海域の調査などから、放水された海水が再び取水口から取り込まれ循環している疑いが強くなっているという。いったん暖められた海水が、十分冷やされることなく、さらに加熱されると、海水温の上昇は加速していく。水温が高い海水が拡散すれば、環境に大きな変化をもたらすのは自明の理である。そこで生息する生き物にも多大な影響を与える。海の資源が枯渇する可能性さえはらんでいるという。
川内原発の場合、川内川の河口にあたる海岸に1、2号機が並ぶ。九州でも屈指の大河である川内川は、多くの栄養分を海に運んでおり、そのため近海はプランクトンが多く、魚や貝を育む場所となっている。一般的に、河口域は陸から供給される栄養分が集積されるため、多くの水生生物の産卵や保育の場所となっているほか、淡水域と海水域を行き来する回遊性のウナギ、アユ、モズクガニなどが一時的に滞在する場所でもある。その環境が変わることで、魚介類の減少を招いてしまうということだ。
「温排水」については、取水-放水システムそのものにも問題があるという。
※記事へのご意見はこちら