
4月21日に建設会社の業界団体である日本建設業団体連合会(日建連)、日本土木工業協会(土工協)、建築業協会の3団体合併の合意が発表された。早ければ来年4月にも合併する。日建連会長は野村哲也・清水建設会長、土工協会長は中村満義・鹿島建設社長、建築業協会会長は山内隆司・大成建設社長であり、全国規模の業界団体統合だ。にもかかわらず、マスコミの注目度は低く、あまり大きく報じられることはなかった。現在の建設業界の苦境を象徴している出来事だろう。
栄華を極めたバブル期
日本の高度経済成長とともに、建設業界は急激に拡大した。交通インフラなどの社会資本整備に加え、企業の積極的な設備投資、旺盛な住宅需要などの内需拡大に牽引されるかたちで、バブル期には栄華を極めた。バブル崩壊を迎えた1990年の建設投資は81.4兆円に上り、崩壊後の経済対策が数値として表れた92年には84兆円におよんだ。GDP対比で17.4%を記録するなど、諸外国と比較しても突出した建設市場は、600万人を超える雇用の受け皿でもあった。
首都圏との若干のタイムラグがあったこともあり、福岡はバブル崩壊後も建設ラッシュに沸いていた。百道地区には福岡ドームやシーホークホテルが完成し、地元放送局の新社屋や大手企業のビルが相次いで建設され、総工費100億円を超える建築工事も珍しくなかった。博多地区でも博多リバレインやキャナルシティ博多などの大型商業施設が完成した。そうした大型物件のほとんどは、スーパーゼネコンを始めとする大手ゼネコンの受注だったが、地場ゼネコンにも恩恵があった。大手ゼネコンとのJV(共同事業体)に参加することもあったが、なにより豊富な需要に支えられていたことで、一定の棲み分けができていた。大手ゼネコンが大型物件に傾注したことで、マンション建築などは比較的、地場ゼネコン優位の受注状況だった。
だが、徐々に福岡にもバブル崩壊の影響が出始め、状況は一変する。公共工事の減少、民間設備投資の減少から受注不足に陥った大手ゼネコンは、以前なら見向きもしなかった小型物件にまで参入し始めた。大手、地場が入り乱れた受注合戦が繰り広げられ、競争に敗れた地場ゼネコンは倒産の憂き目に遭った。
一時的なファンドブーム
経済対策によって一時的に反転した96年以降、建設投資は一貫して右肩下がりの状況に陥った。その後約10年間にわたって縮小が続いてきた業界に、持ち直しの兆しが見え始めたのが05年頃から。依然として公共投資は抑制が続いていたものの、マンション需要を始めとする民需に支えられ、建設投資が51兆円程度で下げ止まった。この時期、民間住宅投資、非民間住宅投資とも対前年比でプラスに転じている。ファンドブームとも言うべき不動産投資が活発化したことで、建設業界は一時的に活況を呈した。同時に、スーパーゼネコンが内需依存での限界から海外へ積極的に展開していたこともあり、再び大手、地場の棲み分けができつつあった。
だが、07年にサブプライムローン問題が表面化したことで、再び市場が縮小し始めた。不動産投資ファンドの勢いに陰りが見え始め、それは08年9月のリーマン・ショックで決定的なものとなった。
SPCを組成し投資物件を建築、ファンドへ売却するビジネススキームは、音を立てて崩れ去った。ファンドが一斉に投資にブレーキをかけたことで、まずデベロッパーが出口を失い閉塞状況に陥った。同時にゼネコンは回収難に苦しむこととなり、商事留置権を駆使しながら保全に奔走した。受注先であるデベロッパーが倒産すれば、巨額の焦げ付きが発生する。倒産しなくても、デベロッパーの大半はファンドへの出口が塞がれた状況でゼネコンへ支払いする資金力はなく、支払いの棚上げが乱発された。またマンション市況も冷え込んだことで、ゼネコンに対して売れ残ったマンションでの代物弁済が続発した。
さらに09年11月には、スーパーゼネコンをドバイショックが襲う。海外に活路を求めていた大手ゼネコンは、巨額の損失計上を余儀なくされることになった。
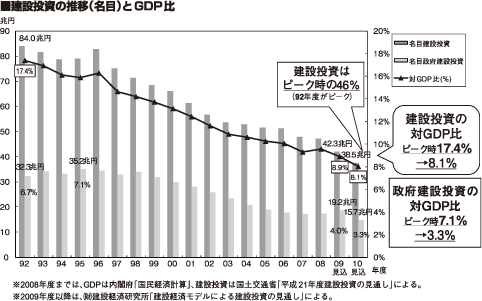
【緒方 克美】
*記事へのご意見はこちら
※記事へのご意見はこちら
