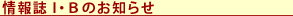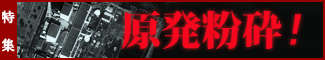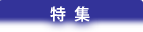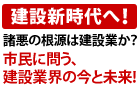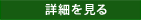特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
経済小説
プロジェクトミーティングのなかでは、サブリース契約の内容について議論を尽くした。新たにマネジメント部長となった牧田部長(後に取締役)は、借上額を満室時家賃の85%とすることを主張した。これであれば、当社が逆ザヤを背負う可能性はきわめて低かった。私もこれに賛成だった。しかしこの85%借上案は、これまで満室時家賃の90%での借上を看板にして物件を売ってきた営業部門からは抵抗が強かった。稲庭部長(後に取締役)ほかの営業部門の一般的な主張は、当社が自信を持ってお薦めする企画物件なのだから、当社が責任をもって借上げるべきであって、そのために賃貸管理部で責任を持って入居者募集をするべきである、というものであったと思う。しかし私は、もちろん入居者募集にも改善するべき点はあるものの、当社の管理物件のシェアは、福岡市内の全賃貸マンションの10%もないため、大勢としては市内の家賃相場と無縁ではない。従って、いくらリーシングで頑張っても市内の家賃相場が下落するなかでは、逆ザヤ解消は困難であると考えていた。数年前までは、DKホールディングスの建物は、意匠に特徴があり差別化が図られていたが、他社の意匠も急速に追いついてきていた。そのため、私は、あらゆる困難を乗り越えて、サブリース問題は解決しなければならないと主張した。
 そもそも当社のサブリースは、契約書にも2年毎の契約更改が盛り込まれており、経済合理性のあるものだった。それが継続不可能なものになったのは、更改がなされずに放置されていたからである。それでも継続できるのならいいが、いずれ管理物件がさらに古くなり、家賃が下がると逆ザヤも拡大し、いずれは限界になる。そのときには、当社の管理物件はもっと増加しており、それらがいっせいに逆ザヤを広げると、会社の収益性を揺るがすようになりかねない。そのときになってサブリースを投げ出してしまっては、オーナーにも迷惑がかかる。当時は、ファンド向けの物件売却で利益を稼ぎ、その稼ぎでサブリースの赤字を埋めていた。しかし、ファンドの需要が長続きする保証もなかった。
そもそも当社のサブリースは、契約書にも2年毎の契約更改が盛り込まれており、経済合理性のあるものだった。それが継続不可能なものになったのは、更改がなされずに放置されていたからである。それでも継続できるのならいいが、いずれ管理物件がさらに古くなり、家賃が下がると逆ザヤも拡大し、いずれは限界になる。そのときには、当社の管理物件はもっと増加しており、それらがいっせいに逆ザヤを広げると、会社の収益性を揺るがすようになりかねない。そのときになってサブリースを投げ出してしまっては、オーナーにも迷惑がかかる。当時は、ファンド向けの物件売却で利益を稼ぎ、その稼ぎでサブリースの赤字を埋めていた。しかし、ファンドの需要が長続きする保証もなかった。
それに、サブリースが実質的に物件販売に欠かせないものになっていて、解約や更改ができないのであれば、当該物件を売却することで本来当社からオーナーに移転されるべきリスクが移転されていないことであり、そうであれば会計上はオーナーに物件を売却したとは認められないのではないかという疑義もあった。その場合は、当社がオーナーに物件を売って代金をもらったのではなく、当社がオーナーに物件を担保として預けて金を借りているとして取り扱わざるを得なくなるのである。
これらの議論から、サブリース問題の解決に向けての合意が形成でき、借上率は、満室時家賃の90%、3年ごとに直近家賃を参照して自動的に借上額を修正する条項を持ったサブリース新契約の案がまとまった。更改期間を3年としたのは、更改頻度を下げることで営業費用を抑えることをねらったのである。物件競争が激化して、募集には常に広告料の支出が付きまとうようになっていたが、募集費用の一部をオーナーに負担していただくことも決められた。
プロジェクト立ち上げと同時に取組んだのが工程表の作成である。
年内にあらかたの契約更改を終えられるように、作業工程を検討した。そのためには、まず、契約を更改するために必要な作業項目をリストアップした。新契約案の作成、会社承認、オーナーへの告知、契約書のデリバリーなどを、9カ月の工程表に落とし込んだ。ここで私がこだわったのが、当社が年4回出していた広報誌『オーナーズクラブ』への掲載である。次の発刊は8月であったから、そのためには、7月中に契約更改案をまとめなければならない。 逆に、この掲載をきちんとこなしてしまえば、その後はおのずと作業せざるを得なくなり、後戻りに対する歯止めになると考えたからである。
新サブリース契約の骨子と、更改スケジュールをまとめたところで、主務担当の江口常務、牧田・稲庭両部長とともに、黒田社長に方針を説明し、了承を得た。黒田社長も、固い意志を持って契約更改を実現してほしい、自分も必要なオーナーには説明に行く、と決意を示した。
このように、課題を明らかにし、役割分担を見直し、プロジェクト体制で契約更改を推進することで、年度内にほとんどのオーナー様から「賃料相場連動式サブリース契約」への同意を取り付けることができたのである。ただし、大半の賃料変更が発生するのは3年後ということであって、直ちに収益性が改善したわけではない。しかし、黒田社長が旗振りをしなくとも、江口・稲庭・牧田といった営業系の取締役・幹部が曲がりなりにも、自律的に、ひとつの方針を決めて不動産管理事業の収益改善の基礎を築いたということで、大きな意味があった。
このプロジェクトの最終ミーティングで私がメンバーに対して力説したのは、もはや各メンバーは、経営課題に果敢に対処し、処方箋を実行に移していくための手法を身につけたので、同じ手法を各部で果敢に活用して必要な改革を行なってほしい、ということであった。
〔登場者名はすべて仮称〕
(つづく)
※記事へのご意見はこちら