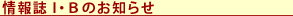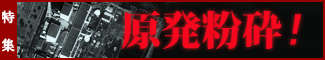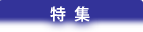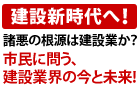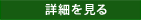特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
読者投稿・ご意見メール
20世紀は原油を基幹エネルギーとし、飛躍的に経済発展を遂げた「油の世紀」であったが、化石燃料は地球温暖化をもたらし、洪水、干ばつなどの異常気象を頻発させた。それ故、21世紀は世界の人口増に伴う食糧問題などから「水の世紀」と唱えられている。
わが国は、毎年15兆円も払って原油を買っているが、「近代技術の証であるダム」は、天からの贈り物である雨水を貯え必要時に利用することで、経済発展、安全確保、生活水準の向上などに多大な貢献をしている。
しかし、2009年に政権を獲得した民主党は、10年、国と水資源機構が事業主体の直轄ダム31事業、国の補助で道府県が建設する補助ダム53事業について、ダム見直しの検証を命じた。その方法は、ダム事業とダムなしの治水案を比較し、"コスト最重視"でダム建設継続の可否を判断するやり方。あたかも、ダムは環境を破壊し、巨額の税金を使う無駄な投資であるかのように取り扱っている。
本稿では、ダムによって水利権を得ている利水側から見た時、「本当にわが国には、ダムは要らないのか」について、考えてみる。
 まず、わが国の河川法におけるダムの位置づけを見てみよう。1896年(明治29年)、明治政府は治山・治水のために、河川法を森林法、砂防法と含めて「治水三法」のひとつとして公布した。戦後は、不足する電力確保のための水力発電、次いで工業用水、上水、灌漑(かんがい)用水の需要増によって、ダムによる河川の高度な水利用や広範囲にわたる水系の管理が必要となり、1964年(昭和39年)、河川法は治水に利水を加えて大幅に改正された。これを機に、水資源開発促進法などの法整備によって利根川、木曽川、筑後川等の7水系を中心に、ダムの建設ラッシュが始まった。97年(平成9年)には、河川に自然護岸を取り入れるなどの環境への配慮をするべきとして、河川法は3回目の改正がなされた。
まず、わが国の河川法におけるダムの位置づけを見てみよう。1896年(明治29年)、明治政府は治山・治水のために、河川法を森林法、砂防法と含めて「治水三法」のひとつとして公布した。戦後は、不足する電力確保のための水力発電、次いで工業用水、上水、灌漑(かんがい)用水の需要増によって、ダムによる河川の高度な水利用や広範囲にわたる水系の管理が必要となり、1964年(昭和39年)、河川法は治水に利水を加えて大幅に改正された。これを機に、水資源開発促進法などの法整備によって利根川、木曽川、筑後川等の7水系を中心に、ダムの建設ラッシュが始まった。97年(平成9年)には、河川に自然護岸を取り入れるなどの環境への配慮をするべきとして、河川法は3回目の改正がなされた。
次に、米国においては、すでに既存ダムが取り壊されているが、その経緯を見てみよう。北米の国民感情は、大いに鮭(さけ)を愛でる気持ちが強いため、鮭の魚道を造ったり、ダム直下で鮭を捕獲し人工授精させて下流に放流したり、ダム築造場所を本川でなく河道外(鮭が昇ってこない河川)に求めるなどで、鮭の産卵のための遡上(そじょう)を手助けしている。
70年、ニクソン大統領は、「国家環境政策法」を制定し環境影響評価書の作成を義務づけ、73年に「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律(絶滅危惧種法)」を制定した。この絶滅危惧種法は、希少動植物を絶滅させず保護する法律で、過去のプロジェクトをもすべて対象とした。この結果、78年、連邦最高裁判所はわずか3インチの絶滅危惧種であった魚を守るために、ほぼ完成したテリコダム建設工事を差し止めた。また、99年にはメーン州のエドワーズダム(水力発電用)を連邦政府の命令で取り壊した。これは、鮭の遡上に魚道の設置が必要で、新たに魚道を築造すれば1千万ドルの工事費を要するが、ダムを撤去すると工事費が半分で済む、という理由であった。
【作者略歴】
 藤井 利治(ふじい としはる) 1944年(昭和19年)9月生まれ。九州大学工学部卒業。福岡市入庁後、福岡地区水道企業団理事、下水道局長、土木局長、水道事業管理者、福岡アジア都市研究所副理事長などを歴任する。2001年、渇水と節水をテーマにした論文で、福岡市職員では初となる工学博士号を取得。著書に『水を嵩(かさ)む』(文芸社刊)がある。
藤井 利治(ふじい としはる) 1944年(昭和19年)9月生まれ。九州大学工学部卒業。福岡市入庁後、福岡地区水道企業団理事、下水道局長、土木局長、水道事業管理者、福岡アジア都市研究所副理事長などを歴任する。2001年、渇水と節水をテーマにした論文で、福岡市職員では初となる工学博士号を取得。著書に『水を嵩(かさ)む』(文芸社刊)がある。
*記事へのご意見はこちら