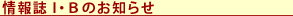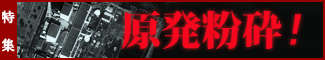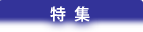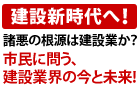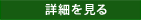特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
未来トレンド分析シリーズ
そこに目をつけた投資ファンドや大手金融機関が、次々と水源地を自らの富を生む資源として独占しようとする動きを、果たして放置していいものだろうか。古くはスイスのピクテ銀行が始めたウォーターファンドを源に、現在ではSAMサステナブル・ウォーターファンド、サラシン・サステナブル・ウォーターファンド、スイスキャンツー・イクイティー・ウォーターファンド、タレノー・ウォーターファンドなど実に多種多様のウォーターファンドが金融商品として、世界中の投資家の間で売買の対象になっている。水関連の企業の株を組み込んだインデックス商品も人気を集めている。水源地の利権を商品化した債権も出回るようになってきた。
 経済危機の時代であればこそ、安定した商品としての水および水関連のビジネスが、かつてないほど投資家の関心を集めつつある。多くの投資家が共通して言うには、「水ほど確実な投資物件はないだろう。インフレの時代にも強く、長期にわたり安定的なリターンが期待できる。必要があればいつでも売って、現金化できるのが強みだ」―こうした投資家の水への渇望感をあおっている最右翼が、ゴールドマン・サックスであろう。
経済危機の時代であればこそ、安定した商品としての水および水関連のビジネスが、かつてないほど投資家の関心を集めつつある。多くの投資家が共通して言うには、「水ほど確実な投資物件はないだろう。インフレの時代にも強く、長期にわたり安定的なリターンが期待できる。必要があればいつでも売って、現金化できるのが強みだ」―こうした投資家の水への渇望感をあおっている最右翼が、ゴールドマン・サックスであろう。
同社の幹部は「アメリカ国内だけでこの2年間に2,500億ドルもの水関連投資マネーを集めた」と豪語している。そうしたノウハウを活用し、ウォールストリートの投資銀行はアメリカから世界に水ビジネスを拡大する動きを活性化しているのである。国内の水インフラの整備事業だけでも今後5年間だけで1兆6,000億ドルのビジネスが期待されている。
世界全体で見れば、水道事業が民営化されているのは8%に過ぎないが、2015年までにはこの数字は確実に倍増するとみなされている。民営化に伴い、水道関連ビジネスはインフラ整備や料金徴収サービスなど、確実に2年で倍増するほどの勢いで拡大中だ。水ビジネスが今後どのようなかたちで進展するものか、世界のウォーターバロンズと呼ばれる水関連企業は、豊かな水源とより安定したサービスを求める消費者の多い日本という新たな市場を虎視眈眈と狙っている。
実は、アメリカ政府が強力に推進しはじめたTPPにも、この新たな水ビジネスは市場開放の重点分野として組み込まれているのである。水ビジネスの覇権争いの場になっているダボス会議で、菅首相が何を嗅ぎとってくるのか、それを日本の国益にどう結び付けるのか、大いに期待したいところである。日本発の水ビジネスを海外展開するには与野党関係なく、オールジャパンで支援体制を組まねばならない。
<プロフィール>
 浜田 和幸(はまだ かずゆき)
浜田 和幸(はまだ かずゆき)
参議院議員。国際未来科学研究所主宰。国際政治経済学者。東京外国語大学中国科卒。米ジョージ・ワシントン大学政治学博士。新日本製鉄、米戦略国際問題研究所、米議会調査局等を経て、現職。2010年7月、参議院議員選挙・鳥取選挙区で初当選を果たした。
*記事へのご意見はこちら