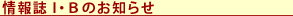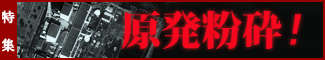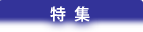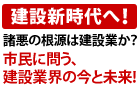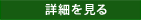特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
深層WATCH
原発建設ブームが始まった30~40年前、「飛行機が落ちても大丈夫」と豪語し、25年前、チェリノブイリ事故が起きると「炉型が違う」「ソ連の原発は建屋が脆弱。日本の原発はジャンボが落ちても大丈夫」と言ったのは誰か。東電福島第1原発の惨状を見れば、日本の電力業界がいかに誇大妄想のウソつきだったかがわかろうというもの。その業界でヒネた聞きわけのないガキ大将のように振る舞ってきたのが東電だ。
 爆発で舞い上がる粉塵と水蒸気の後に現れたのは、屋根と壁が吹き飛んで鉄骨むき出しの原子炉建屋の無惨な姿。見た目はまさにチェリノブイリ事故そのまま、第1原発の現状は行方の見えない「放射能の恐怖」をさらけ出している。
爆発で舞い上がる粉塵と水蒸気の後に現れたのは、屋根と壁が吹き飛んで鉄骨むき出しの原子炉建屋の無惨な姿。見た目はまさにチェリノブイリ事故そのまま、第1原発の現状は行方の見えない「放射能の恐怖」をさらけ出している。
ただ3月19日になり、東京消防庁のハイパーレスキュー隊や陸上自衛隊特殊部隊による本格的放水が始まり、事故はヤマを超えられる可能性が出てきた。すなわち地震発生から1号機爆発に続き、第1原発6基中の4号機まで次々と大事故が発生。それぞれどう抑え込めるか、見通しがまったく立たない日々が続いた。それが19日の東京消防庁、陸自部隊による各原発への放水による冷却効果が見えてきつつあるからだ。
事故は11日の地震直後に1号機の異変から始まり、翌日の爆発でレベル5級大事故は必至だった。原子力災害の評価には7段階あり、レベル7という原発史上最大の事故がチェリノブイリ(1986年。旧ソ連ウクライナ)、史上2番目がスリーマイルアイランド(TMI事故。79年。米ペンシルベニア州)のレベル5だ。中間のレベル6に旧ソ連で起きた「ウラルの核惨事」(57年)とよばれる事故があった。こちらは原子爆弾開発に使った核廃棄物の貯蔵所で起こった核爆発により、ウラルから旧ソ連一帯が被災したが、当時は『鉄のカーテン』に閉ざされて実態はもとより、事故そのものが世界に知られることはなかった。
したがって原発大事故として知られているのが先の2例。いずれも数基あるうちの1基が事故を起こしたものだが、福島第1も1号機の水素爆発により建屋が吹き飛んだところでTMI級事故になるのは必至だった。同じ炉心溶融でもTMIでは外見上の建屋損傷はなかった。それだけ1号機内の炉心溶融は激しく、TMIを超える可能性をも予感させた。実際、13日~14日時点で京大原子炉実験所の今中哲二、小出裕章両助教授らは、取材に「1号機で起きたことは他の炉でも起こる。TMIは超えた。これからチェリノブイリに向かうか否かの瀬戸際」と明言した。
ところが政府の当初評価はレベル4。いかに事態を甘く見ていたかの証左だ。レベル4は99年に茨城県東海村の核燃料製造工場(JCO)で起きた臨界事故と同レベル。JCO事故では発生2時間後に村が住民に350m圏内からの退避を要請。10時間後には県が10km圏内での屋内退避を勧告するなど、何もしない政府に代わって自治体が自主判断。政府はそれを追認するだけだった。
今回、事故は先の京大グループの研究者たちの予測通りに2号、3号、4号へと拡大。政府が事故評価をレベル5に引き上げたのは18日になってからだ。この間、住民への退避勧告範囲も当初の3km圏から10km、そして20~30kmと、効果のない景気対策のようにチビチビ拡げたのは周知の通り。この間は政府も東電も有効な手を打てないないまま、チェリノブイリ側に振れるか、TMI側で踏みとどまるか、まさに瀬戸際が続いたし、いまも続いている。各炉への注水体制は整いつつあるものの、それをどう維持していくか長期戦になるからだ。
そこで問われるのが政府や東電の当事者意識、能力だ。事故発生当初から現場での対応はもとより、情報公開も説得力を欠いて国民の不信を招くなど、信頼できないからだ。
| (後) ≫
恩田 勝亘【おんだ・かつのぶ】
1943年生まれ。67年より女性誌や雑誌のライター。71年より『週刊現代』記者として長年スクープを連発。2007年からはフリーに転じ、政治・経済・社会問題とテーマは幅広い。チェルノブイリ原子力発電所現地特派員レポートなどで健筆を振るっている。著書に『東京電力・帝国の暗黒』(七つ森書館)、『原発に子孫の命は売れない―舛倉隆と棚塩原発反対同盟23年の闘い』(七つ森書館)、『仏教の格言』(KKベストセラーズ)、『日本に君臨するもの』(主婦の友社―共著)など。
*記事へのご意見はこちら