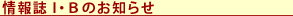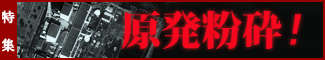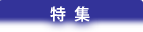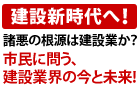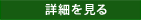特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
東京レポート
10月29日。ファミリーレストラン「すかいらーく」は、川口新郷店(埼玉県)を最後に39年の歴史に幕を閉じた。今後は低価格店の「ガスト」などに転換を進め、「すかいらーく」ブランドは社名として残るだけとなった。ファミリーレストランの衰退が唱えられて久しいが、「すかいらーく」の閉店は、ファミレス時代の終焉を改めて見せつけた。
<ファミレスのひとり負け>
外食産業の低迷は続いている。外食産業の市場規模は、1997年の29兆円をピークに減少を続け、近年は24兆円規模にとどまる。このうち半分の12兆円が飲食店の市場規模。景気後退で、市場規模はさらに縮小するのは確実。そのなかで、業績の二極化が一段と鮮明になった。
好調組は、特色ある単品メニューで勝負するハンバーガーの日本マクドナルドホールディングスや餃子の王将フードサービスなど。苦戦を強いられているのはファミリーレストラン。すかいらーくは、08年8月に創業家出身社長を解任し、野村プリンシパル・ファイナンス(野村ホールディングスの子会社)の傘下で再出発。その再建策として、創業事業であるファミリーレストランの看板を下ろした。
社団法人日本フードサービス協会がまとめた08年の外食産業の売上高は、前年比101.3%と前年をわすかに上回った。落ち込みが最も大きかったのはファミリーレストランで、前年比98.4%とマイナス。ファーストフードが売り上げを伸ばしているのに反し、ファミリーレストランだけがひとり負け、である。なぜ、ファミレスは衰退を速めたのか。
<大阪万博が外食元年>
日本の外食産業にとって、外食元年と位置付けられているのが70年の大阪万国博である。城山三郎氏の小説『外食王の飢え』のモデルとして知られるファミリーレストラン・ロイヤル(現・ロイヤルホールディングス、福岡市)の創業者・江頭匡一氏(故人)が、急成長のきっかけを掴んだのは大阪万博の米国館への出店だった。
大阪万博では、米国館の人気は格別。アポロ宇宙船が持ち帰った「月の石」を一目見ようと、長蛇の列が続いた。ロイヤルは、米国ゾーンでカフェテリア・レストランをはじめ、ステーキハウス、ハワード・ジョンソンショップ、ケンタッキー・フライド・チキンの4店舗を出店した。
江頭氏は『私の履歴書』(日本経済新聞社刊)のなかで、大繁盛ぶりをこう記している。
『店では毎日、ステーキが二千枚、ハンバーグも二千枚というような盛況ぶりだった。当初は、約六ヵ月の会期中に七億円の売上高があればトントンと踏んでいたのに、締めてみると軽く十一億円を超えた。ロイヤルの店の倍の広さがあるソ連館でさえ、売上高は七億円。それを大きく上回り、会場内の各国レストランのなかで期間中の売上高一位で、表彰された』
大阪万博での成功をバネに、ロイヤルは郊外型ファミリーレストランに進出。71年暮れ、その先駆けとなるロイヤルホスト第1号店を北九州市八幡西区に開店した。
一方、東京郊外の国立市では、スーパーを経営していた横川4兄弟が、70年7月にスカイラーク第1号店(当時はカタカナ表示)を創業。ファミリーレストランの歴史は、ここから始まる。
【日下 淳】
*記事へのご意見はこちら