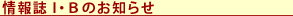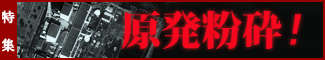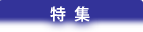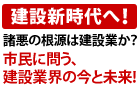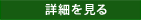特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
経済小説
野口 孫子
権力掌握への執念 (2)
坂本は2年がかりで、自分の意のままになる体制の構築を考えていた。建前のうえでは、社長は取締役会で決める。取締役会は株主が集まって選ぶ。だから「株式会社は株主のものだ」と言われる。しかし、そんなことを本気で信じる者はいない。
現実には、取締役は社長が選ぶ。「取締役会は社長の独演会」「会社は社長のもの」。それが現実の姿である。このことは坂本が一番よく知っていた。
6年前、創業社長が死去したあと、営業業績が伸び悩んだ時期があった。その際、営業畑の会長・渡部と経理畑の社長・中井が会社の実権を巡って争い、取締役を会長派と社長派に二分したことがあった。坂本はそのとき、重要な役割を演じた。
「わしの眼が黒いうちは、わしが営業の指揮を執る」と言っていた山田がいなくなった時、各地の営業系役員から「中井体制では、営業は活性化できない。この際、営業の師と謳われている渡部哲志会長に社長を兼務していただき、陣頭指揮を執ってほしい」という動きが出てきた。
山田は会長へ退くとき次期社長に渡部を指名するのではないかと思っていた役員、幹部は多かった。しかし、親会社である山水工業の意向も忖度せねばならない。渡部は親会社の出身でなかったし、山水工業が山水建設と競合する事業を展開していたため、渡部は先頭に立って、親会社批判を繰り返していた。
当時、末席の平取締役だった坂本は、権力闘争の凄まじさを目の当たりにしたのである。この時の経験が、のちの社長就任にあたり、役員および主要幹部の人事権は絶対に自分が握ると決意することにつながるのである。社長は絶対的権力を持っている。しかし、取締役会で多数派を形成することができなければ、「寝首をかかれることになりかねない」ことを体験したのである。
当時、日頃から「生涯現役でやるんだ」と豪語していた山田は、自らの体調に対する自信を喪失しつつあった。そしてついに、経理畑一筋で営業経験はもちろん、営業の指揮を執ったこともない中井専務を社長に指名したのである。山田としては、苦慮した末の決断であった。
「親会社出身の中井なら支障はない」「渡部営業担当副社長だと、日頃の言動からして、親会社の反対が想定される」と踏んで、自らは会長となり、中井を社長に、渡部を副会長としたのである。
この決定に対し、渡部に育てられ、師と慕い、渡部社長を待望していた営業系・技術系役員のなかから、反対の声がわき上がったのであった。副会長という閑職に追いやられた渡部をおもんぱかり「なぜ、営業のわからない人が社長なんや? 中井に経営ができるわけがない」との意向を示す者が少なくなかった。しかし、20年も社長の座に君臨していたカリスマ・山田に対し、面と向かって反対を唱える者は誰もいなかった。
山田もそんな状況を把握していた。
「中井は営業はわからんが、わしの眼の黒いうちは営業はわしが見る」
そう声高に宣言し、反対論を一蹴したのである。
ところがこの頃から、山田の体は癌という病魔に蝕まれていたのである。さすがの山田も病魔には勝てず、中井を育てきれないまま、この世を去ってしまう。そして、山田が後継者を育てておかなかったことのツケが、彼の死後すぐに中井と渡部の権力闘争というかたちで現れた。
カリスマ・山田亡きあと、渡部を担ぐ一派の間で、中井降ろしの動きが激しくなっていく。空席となった会長の席を埋めるため、渡部が会長に就任し、それでことは収まるかと思われた。
ところが、「この際、一気に渡部を社長に!」と渡部を信奉する役員たちの動きが活発になってきた。
取締役会、全国幹部会などの会議において、渡部・中井による公然たる激論が参会者の前で口汚く展開された。
「あんたみたいな素人に、営業の気持ちがわかるわけがない」
「あんたは黙れ!業務執行最高責任者は社長のわしや!」
2人の対立は、見るに耐えない泥試合の様相を呈していた。
いずれの陣営につくものか、旗色を鮮明にしている役員数は、ほぼ互角であった。中立派もいたが、露骨にしかめ面をしている者、旗色のいい方につこうとして様子見をする者など、それぞれであった。
株式会社の社長には絶大な権力があるが、その最たるは『人事権』を持っていることだ。サラリーマンは取締役になることを夢見ている。取締役を選任するのは社長である。常務、専務、副社長を選任するのは社長であり、罷免するのも社長だ。
中井は先輩の渡部と強気で戦った。一方の渡部一派は営業系の大半を押さえていたが、新参の営業系役員の坂本だけが渡部の誘いに乗らなかった。
そのときすでに、坂本は中井に一本釣りされていたのである。
次の役員改選時には「君を常務に」という言質を中井からもらった坂本は、中井一派に与することを決めた。営業系の役員を味方につけたことは、営業のことを知らない中井にとって大きな力となったのだった。
(つづく)