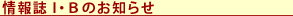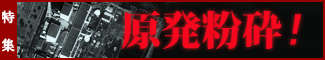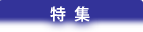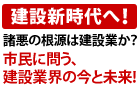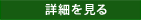特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
企業、人 再生シリーズ
<外資撤退。窮地に追い込まれてゆく>
アメリカで起こっているサブプライムローン問題は毎日のようにマスメディアをにぎわせた。新聞、テレビ、経済誌からゴシップ誌に至るまで、アメリカ経済のほころびをあらゆる角度から取り上げていた。黒木のもとにも、会社の行く末を案じ、というよりは自分の取り分を案じて多くの人が押し寄せるようになる。
8月に入るといよいよ状況は押し迫ってきた。外資系ファンドが一気に日本から撤退を始めたのだ。本国での経営課題があまりにも大きすぎたため、日本にマンパワーを割くことができなくなったのである。外資系の引き際は鮮やかだった。まるでスタートライン上に並び、スタートピストルを鳴らしたかのように一斉に本国へと帰っていった。黒木にとって、それは大型プロジェクトの座礁を伝えるものだった。
状況を見切った銀行は、各取締役を飛び越えて、直接、黒木を訪ねてくるようになった。現在進行中の案件はほとんど全てが取締役を通じて融資を受けてきたものであり、それぞれに対して黒木が銀行と折衝することはなかった。前年まで、黒木が銀行とすることといえば、銀行側の支店長や頭取と食事会をしたり、親睦を深めたりすることくらいだった。それにもかかわらず、各案件の責任者である取締役を通り越して黒木と直談判するようになったのである。
都銀の取締役たちは頻繁に黒木を指名して訪れる。進捗状況、預金残高を確認してくる。ある地銀は黒木の資産を売却して損失を埋めることを強く要望してきた。ディックスクロキとは別に個人でやっていた会社の資産まで売却するように促す。黒木はそれを断り続けた。
「ディックスと私の個人で経営している会社とは別問題ですし、私の資産も別のことです。ですから、穴埋めに使うという理由がないので応じることはしませんでした。何より私の個人資産を売却したところで、埋められる損失は極わずかです」
黒木の個人資産を損失に充てても焼け石に水であることは双方ともに分かっていた。それにもかかわらず、そのような要望を出すのは道義的な理由からだったと思われる。けれども、仮に黒木が資産を損失にあてがっても、その先を銀行が保証してくれるものではなかったのだ。追加で融資をしてくれる約束もないし、存続を援助する方針に変えてくれる確証もない。これでは到底応じることはできなかったのである。
【柳 茂嘉】
*記事へのご意見はこちら