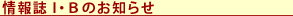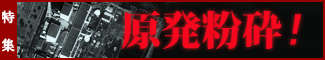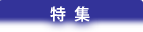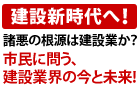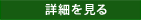特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
企業、人 再生シリーズ
<終止符を打つ覚悟を決める>
栓の抜かれた風呂桶のように、これまでの蓄えが流れ出ていく。大きなプロジェクトの穴を埋めるためには仕方のないことではあったが、黒木にとっては自らの血が流れるのに等しい痛みを伴った。独立して以来、さまざまな困難に打ち勝って得た社の資産がみるみるうちに減っていってしまうのだ。35億あった内部留保が億単位で消えていく。それでも一筋の勝機が来ることを願いつつ黒木は耐えた。耐え続けた。
2008年9月15日、世界中を1つのニュースが駆け巡る。3月のベアー・スターンズに続く、全米4位の証券会社、リーマン・ブラザーズの破たんである。負債総額64兆円という過去に類を見ない破たんはアメリカのみならず世界に影響を与えた。日本もその余波を被り、日経平均株価が7,000円台にまで落ち込むことになる。海を越えてきた激震に日本の金融機関も揺れた。アメリカの好況に頼ってきたつけが一気に回ってきたのである。日本の銀行はより態度を硬化した。平成不況を乗り切る一縷の光が見えてきた矢先の、大きすぎるつまづきだった。
黒木のもとにも大波が襲ってきた。銀行が担保権の留保を言ってきたのだ。担保権の留保とは、完済がなされていない取引において、目的物(この場合は土地)の所有権を留保するというものだ。すなわち暫定的に土地を銀行のものにするという宣告である。土地の権利は銀行に抑えられてしまった。黒木が期待していた追い風はついに吹かなかったのだ。
袋小路にはまってしまった。右に行くにも左に行くにも動きが取れなくなってしまった。黒木の頭の中に破たんが浮かぶ。やるだけのことはやってきた。それは自他共に認めるところだった。けれども大きく開いた帆船の帆は、より大きく逆風を捉えてしまった。行き足が止まるどころか、一気に転覆の危機に陥ってしまった。もはやどうすることもできない。
10月に入り、黒木は覚悟を決めた。社に残された資産は10億を切っていた。どうすることもできない。ならば、いかにソフトランディングさせるかが問題ではないか。まだ力が多少なりとも残っているうちに次の手を打たねばならない。なるべく協力会のメンバーやゼネコンに迷惑をかけない方法で、幕を閉じなくてはならない。それが経営者の責任。黒木は残された最後の力を振り絞って、最後の作業を開始することにした。
【柳 茂嘉】
*記事へのご意見はこちら