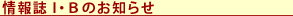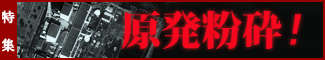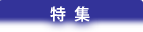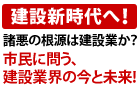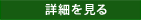特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
特別取材
【(株)千鳥饅頭総本舗~内紛の鎮静化、そして新たな課題(上)】に続き、 (株)千鳥饅頭総本舗で何が起こり、問題となっているのかを述べていく。
意志決定者が見えてこない経営陣
 現在は、ウルズラ夫人が千鳥饅頭総本舗の代表取締役社長に就任している。光博氏とウルズラ社長は、長男・浩司氏(1972年生)、次男・健生氏(1975年)、三男・広太郎氏(1978年)の3人の男児をもうけた。いずれも父にならい、ドイツ留学を経験。現在は、千鳥饅頭総本舗の経営に携わっている。浩司氏が専務、健生氏は常務で金融機関対応、広太郎氏は社長室長として広報的な役割を担っている。
現在は、ウルズラ夫人が千鳥饅頭総本舗の代表取締役社長に就任している。光博氏とウルズラ社長は、長男・浩司氏(1972年生)、次男・健生氏(1975年)、三男・広太郎氏(1978年)の3人の男児をもうけた。いずれも父にならい、ドイツ留学を経験。現在は、千鳥饅頭総本舗の経営に携わっている。浩司氏が専務、健生氏は常務で金融機関対応、広太郎氏は社長室長として広報的な役割を担っている。
兄弟の1人は自ら「かつてうちも内紛があったので...」と自戒をこめて話す。親世代の経験を反面教師にしようという決意がうかがわれるが、肝心の組織運営の形態が見えてこない。「誰が経営判断を行なっているか」という問いに対しても、「さまざまな意思決定は4人で行なっている。『誰がどれ』という単純なものではない」と答える。
役員はさまざまに変遷している。光博氏が存命中の07年10月に次男・健生氏がいったん代表に就任し、一時期は光博氏との2人代表制を敷いていたこともある。この件について同社は、「病気の件があったので、そういう対応をした」としている。時期を考えれば、光博氏の意向が反映されたとするのが自然だろう。
その後、それから4カ月も経たない08年2月に、光博氏と健生氏が代表を辞任。このタイミングでウルズラ氏が代表取締役に就任している。始めからウルズラ氏との2名体制を敷かなかったのはなぜか。
もうひとつ不可解なのは、3兄弟そろって取締役として社業に取り組んでいたのに、07年12月に広太郎氏のみが取締役を辞任していることだ。その理由も判然としない。
そして、チョコレートの「アナベル」で東京に基盤を築く決意で臨んだ浩司氏は、東京の店舗を閉鎖して福岡に復帰。新たに専務に就任した。アナベルは「東京に販路を開拓してアンテナショップとしての役割は果たした」としているが、アンテナショップを企図しての出店ではなかった。そして中洲の店舗を7月31日をもって撤退した。
持分不動産は整理してきたはずだったが、中洲の物件は7者が所有している。立地は中洲の幹線沿いという理想的な条件ながら、独断で手を付けられない状況となっている。ここにきて、終わったはずの先代の同族の課題が収束していないことが明らかになった。
多くの千鳥饅頭総本舗の不動産は会社名義でなく、ウルズラ氏個人の名義となっている。1人に集約されたことでかつてほどの複雑さはないが、今後法人としてどうするか、次の相続問題をどうするのか、といった課題が生まれている。
近年、売上高は緩やかに低下している。10年3月期は約20億1,000万円。店舗撤退などでジリジリと低下している。体質強化を図っている過程であることを鑑みると、減収よりも売上構成の中身に現況が現れている。商品別の構成比は千鳥饅頭とチロリアンが拮抗して約30%ずつ。パンのスベンスカが約10%。残りの20%が、そのほかのアイテムということになる。チロリアンが登場して48年。ほぼ半世紀にわたって、2つの商品だけが業績を支えていることになる。別事業として光博氏が取り組んできた「スベンスカ」が、千鳥饅頭を超えるものに育っていれば、相続争いは違ったかたちになっていたのではないか。仮に、相続争いを早期に決着して、新たなヒット商品を生み出していればどうだったか。結果を見れば、2大商品にしがみついた結果という見方もできる。
「チロリアンアイス」の開発や「アナベル」への注力など、新機軸への挑戦はうかがわれる。チロリアンアイスはかつての支持層への話題性は高かったが、商品特性や取り扱い店舗の問題もあり、業績に寄与する段階ではない。そして、アナベルは東京の店舗から撤退した。
【鹿島 譲二】
*記事へのご意見はこちら