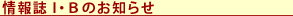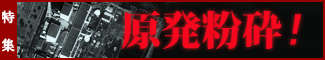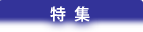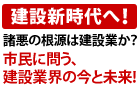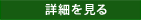特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
特別取材
日本航空(JAL)は1月19日、昨年の会社更生法の適用申請からちょうど1年を迎えた。表面的な営業数値は円高急進による海外旅行客の増加などを受けて好調だが、経営側、労働組合側双方に依然として変わらぬ古い体質がうかがえる。何が変わり、何が変わらないのか、JALの1年を検証する。
それは古色蒼然たる左翼の決起大会だった。
 1月19日水曜日、東京・霞が関に近い虎ノ門の会議室で、JALを「整理解雇」されたパイロットやスチュワーデスが「不当解雇を撤回する裁判闘争」を始めるという記者会見を開いた。会見場には制服姿のパイロットやおそろいのオレンジ色のスカーフを巻いた客室乗務員(スチュワーデス)が数十人集まり、席上にはJALの乗員組合、キャビンクルーユニオンの各委員長、さらには全労協や東京地評など支援する労働団体の幹部ら約10人が勢ぞろいした。
1月19日水曜日、東京・霞が関に近い虎ノ門の会議室で、JALを「整理解雇」されたパイロットやスチュワーデスが「不当解雇を撤回する裁判闘争」を始めるという記者会見を開いた。会見場には制服姿のパイロットやおそろいのオレンジ色のスカーフを巻いた客室乗務員(スチュワーデス)が数十人集まり、席上にはJALの乗員組合、キャビンクルーユニオンの各委員長、さらには全労協や東京地評など支援する労働団体の幹部ら約10人が勢ぞろいした。
もちろん、民放のテレビカメラや記者クラブ加盟の大手紙の記者たちもつめかけたが、記者席に意外に多かったのは左翼系のミニコミ紙や専門誌の記者・編集者たちだった。スーツ姿の若い記者たちに交じって、白髪の長髪や古びたジャンパー姿の「高齢」の左翼記者たちが陣取っていた。
JALは2010年12月9日、管財人である片山英二弁護士名でパイロットとスチュワーデス165人に解雇通知を送り、同月31日全員を解雇した。このうち146人が原告となって1月19日、東京地裁に解雇を無効とし、原職への復帰を求める訴えを起こしたのである。
会見では山口宏弥原告団長が冒頭「多くの原因は国にあります。国の責任は不問に付されています。安全をとるのか、利益をとるのかの闘いです」と説明、当日配られた資料には「市場原理主義の航空政策を改めさせ、利用者国民の期待に添った再生を実現していく」「『利益優先』より『安全最優先』とし、『安全性』と『公共性』を確保した公共交通機関としてあるべき姿をめざす」などとある。まるで、儲けてはいけない、とでもいうかの内容だった。「親方日の丸」意識は経営陣だけでなく、非主流派の労組幹部の側にも強くある。
戦後の高揚した労働運動によって、資本主義社会にあっては特異なことだが、日本の企業は経営側の都合で従業員を馘首することがきわめて困難になった。解雇を規制する法律が定められているわけではないのだが、裁判所の判例によって「整理解雇の4要件」が満たされて初めて解雇できるからだ。4要件とは、(1)企業が経営危機下にあって人員削減の必然性があること、(2)企業側が希望退職の募集や配置転換など解雇回避の努力を果たしていること、(3)解雇対象者を客観的公平に選んでいること、(4)労使協議を十分に行なうなど妥当な手続きを踏んでいること――である。安易に解雇できないよう裁判所が設けた『規制』だ。おかげで企業側は採用に及び腰となり、派遣労働者や請負労働者を多用するようになった。大企業の正規雇用の従業員にとっては有利な規制である。
【特別取材班】
| (2) ≫
*記事へのご意見はこちら