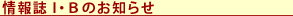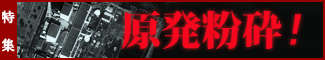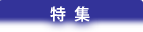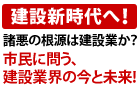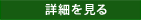特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
深層WATCH
現在、免疫細胞療法の使用権を持っているのは数社あり、開発権者の技術的特徴から「活性化自己リンパ球療法」(株)メディネット、(株)リンフォテック、「免疫細胞BAK療法」(株)共生医学研究所、「樹状細胞ワクチン療法」テラ(株)、「ANK自己リンパ球免疫療法」リンパ球バンク(株)などの治療名で、提携する医療機関が受け付けるシステムだ。
ただ免疫細胞療法に共通する難点のひとつが、受け付ける医療機関のほとんどが東京や大阪などの大都市にあり、月2回としても地方の患者には交通費、時間の負担とも大変なことだ。とくに、共生医学研究所とその専門医療機関「きぼうの杜クリニック」の「BAK(バック)療法」は、培養される細胞が通常は20~30億個であるのに対して約100億個と高く、「他の療法の有効性は10数%から20%ですが、私どもは70%台です」(高橋傑代表)とその有効性を誇るが、本拠は仙台市。患者も事業主体も不利は否めなかった。
ところが昨年4月、厚生労働省の通達によって複数の医療機関が協力して免疫細胞療法が行なえるようになった。そのため現時点までに北海道から九州まで共生医学研究所が全国22カ所、同じくテラも16カ所、リンパ球バンクが関東から九州まで21カ所の医療機関と提携するなど、交通費と時間の問題は解消されつつある。
それでも保険適用外の免疫細胞療法最大の難点が治療代の高さだ。培養は専門技術者の手作業に頼るため、培養センターの運用費が高くならざるを得ないからだ。各社とも1クール12回とすれば150~300万円にもなる。
 ところが、「自分の血で免疫力を高めるという独自の療法に着目すれば、コストダウンは可能」と言うのは、長年米国に滞在して特許技術や製品を日本に持ち込んでいるバウンティーズ・オブ・アメリカズ代表の水谷欽一氏。同氏は酸素水をはじめ、健康、医療関連サプリメントも日本へ多数送り出しているが、拡大する日本のアンチエイジング市場を念頭に、免疫細胞療法の汎用性に注目する。
ところが、「自分の血で免疫力を高めるという独自の療法に着目すれば、コストダウンは可能」と言うのは、長年米国に滞在して特許技術や製品を日本に持ち込んでいるバウンティーズ・オブ・アメリカズ代表の水谷欽一氏。同氏は酸素水をはじめ、健康、医療関連サプリメントも日本へ多数送り出しているが、拡大する日本のアンチエイジング市場を念頭に、免疫細胞療法の汎用性に注目する。
「免疫細胞療法自体は、もともとは米国の海軍病院が中心になって研究、開発してきたもの。戦場での銃創や熱傷、ケガをいかに速く回復させるかは軍隊にとってきわめて重要。免疫力を高めることにより、手術や薬剤による治療効果を速めるのが目的です。また、海軍のシールズ(SEALs)をはじめとする特殊部隊員の体力増強にも必須のアイテム。日本で同様の研究をしているのが防衛医科大および同校出身ドクターであるように、もともとは軍医学です」(水谷氏)。
米海軍病院の血液関連の研究は全米一で、たとえば普通の医学者が「根拠なし」とする血液型性格判断も各血液型をさらに細かく分析し、「根拠あり」としているという。
「潜水艦乗員のように何カ月も密室に閉じ込められた生活が続く場合、乗員同士の相性が重要な要素になる。チームワークと血液型の因果関係を長年のデータから分析、整理してあり、それに基づいて乗員編成するのが当り前になっています」(水谷氏)。
そんな海軍病院が特殊部隊員の体力維持、増強に免疫細胞療法を取り入れているところからまず考えられるのが、プロスポーツ選手による利用だ。培養するのが自分の血であれば、薬剤と違ってドーピング検査に引っかかる心配もない。さらに、お金にも困らない若い全盛期に血を培養して凍結保存。体力が下降線に入ったときに注入すれば、延命にも繋がる。
スポーツ選手同様に需要が見込めるのが、女優やタレント、モデルなど。これに一般の健康、美容にお金をかけることをいとわない富裕層はいくらでもいる。すなわち、免疫細胞療法には本来のがん治療以外にスポーツ医学、美容医学などさまざまな分野に応用できるというのが水谷氏の見方。実際、同氏の見解に賛同する医療関係者もいるというから、アンチエイジングとがん免疫療法のコラボレーションは意外に早く実現する可能性がある。
さらに、ともに自由診療ということもあり、免疫細胞療法を受けるクリニックが、一方でアンチエイジング療法も手がけているケースが少なくない。その意味で、両者の接点はもとから近いともいえる。
いずれにしろ免疫細胞療法の普及が進むほどに治療費が安くなるのは間違いないところ。がん患者には朗報だろう。
(了)
恩田 勝亘【おんだ・かつのぶ】
1943年生まれ。67年より女性誌や雑誌のライター。71年より『週刊現代』記者として長年スクープを連発。2007年からはフリーに転じ、政治・経済・社会問題とテーマは幅広い。チェルノブイリ原子力発電所現地特派員レポートなどで健筆を振るっている。著書に『東京電力・帝国の暗黒』(七つ森書館)、『原発に子孫の命は売れない―舛倉隆と棚塩原発反対同盟23年の闘い』(七つ森書館)、『仏教の格言』(KKベストセラーズ)、『日本に君臨するもの』(主婦の友社―共著)など。
※記事へのご意見はこちら