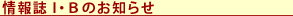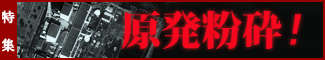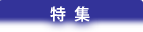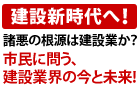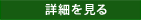特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
経済小説
自由競争市場のなかにいる企業である以上、周辺環境が変化することは当然念頭に置いておかねばならない。自社が置かれた環境の変化があることを事前に予測し、必要な対策をとっておき、しかも変化が実際に生じたときに素早く対応できるように常にアンテナを張っておくことは、経営陣の当然の義務である。企業は、存在する限り、変化に対応していくことが宿命付けられているのである。
 同じ不動産開発業でも、生き残れた会社と倒産を選択した会社がある。その違いは、純資産の充実度や銀行折衝の巧拙だけではない。同じように純資産の薄い新興企業でも、物件を何とか売り切って生き残っている会社もあるのだから、バブルの崩壊や純資産が薄かったことだけではステークホルダーへの説明として不十分である。
同じ不動産開発業でも、生き残れた会社と倒産を選択した会社がある。その違いは、純資産の充実度や銀行折衝の巧拙だけではない。同じように純資産の薄い新興企業でも、物件を何とか売り切って生き残っている会社もあるのだから、バブルの崩壊や純資産が薄かったことだけではステークホルダーへの説明として不十分である。
外的要因が急激に変化したときに、何らかの対応をとる企業がほとんどであろう。値下げしてでも在庫を売り切る。人員を減らし経費を削減する。日銭商売のなかで何とかやりくりしようとする。当社もそうであった。そうしたなかでも、企業は時間とともに倒産を余儀なくされるグループと、何とか存続できる企業に色分けされてくる。その差は、どこにあるのか?そのときの在庫の内容か、従業員の能力か、銀行との交渉の良し悪しか。日銭商売の有無か。これらの要因はすべて企業の存続可否を分けるだろうが、それ以前に、これらのすべては経営陣の能力に帰することである。
繰り返すが、外的要因の変化による倒産であるからといって、経営陣はその責任から逃れることはできない。社長以外の経営陣も会社の機関としての取締役であり、取締役会の議決により企業を運営する限り、倒産に対しては代表者と同等の責任を負う。
所有と経営が分離され、代表者による債務保証もない上場会社の場合は、よほど違法行為などがない限り経営陣が債権者から訴えられることはないだろう。上場会社であれば、少なくとも取締役会や監査役会などの内部けん制機能も働いており、善管注意義務は十分に果たされていると考えられるからだ。
ただ、だから責任を免れたというように考えるのではなく、民事再生法の主旨に沿って弁済をなし、一部事業でも継続を図り、社員の雇用をできる限り確保しつつ、最後まで会社の後始末に当たることで、その道義を果たしていかなければならないと思う。
〔登場者名はすべて仮称〕
(つづく)
≪ (146) |
※記事へのご意見はこちら