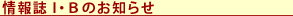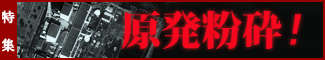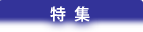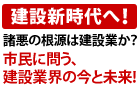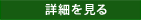特 集
脱原発・新エネルギー
九州から興す!日本経済
士業事務所 戦略シリーズ
東日本大震災
倒産を追う
直撃インタビュー
業界を読む
東京レポート
2011統一地方選挙
自立する地域社会
追跡!裁判事件簿
検証ベスト電器
糸島ローカルビジョン
動画チャンネル
特別取材
経済小説
クローズアップ
コラム・寄稿
コダマの核心
深層WATCH
政界インサイドレポート
清明がほえる
チャイナビジネス最前線
上海最先端レポート
中洲バトルロワイヤル
ハマタケがほえる
未来トレンド分析シリーズ
大手食品営業マンの告白
地域づくりにマーケティング発想を
福岡への提言
歴史の虚像と実像
今、歴史から元気をもらおう
読者投稿・ご意見メール
連載コラム
最新情報
耳より情報
企業
経済
流通
建設
住宅・不動産
健康・医療
最新金融情報
政治
行政
社会
発信!北九州
信用調査レポート
倒産情報(九州・山口)
倒産情報(全国)
イベント情報
セミナー情報
新商品・新技術
チャイナビジネス最前線
わたしは日中国交回復の前年、1971年に就職活動をして、翌年、トヨタ自動車に入社した。当時は、名古屋で卓球大会が行なわれ、アメリカと中国間の外交につながった、いわゆる「ピンポン外交」の時期だったが、最初の仕事は中国の自動車産業視察団を日本に招へいする事業に携わった。1978年、鄧小平が改革開放に舵を切ってから、自動車産業の最も大きな争点は、「対外開放で外資と協力して発展させるか」、それとも「自力更生で資源を集中して、国産能力を高めるか」という2つの選択だった。
前者では、第一汽車に対し、トヨタの生産方式を2回にわたり技術指導のために長春に赴いたりしている。トヨタと中国の結びつきはこの時期から始まったと言っていい。この間に、地方の国営企業は、独自に海外メーカーと接触を始めていて、北京AMCチェロキーや上海VWなどが80年代前半に出てきた。
 当時のピークの、1985年には、完成車の輸入台数が25万台に達し、そのうちのトヨタは10万台を占めるに至っていた。そしてそのころ、「技貿結合」と称して、外貨不足と技術移転を急ぐという理由から、主に日本メーカーに対して、中国に技術の無償導入を求めてきた。いわゆる"市場を以て技術を要求する"動きの始まりとなったのである。ただ、当時、車の図面が平気で本屋に売っていたこともあり、技術に対して、ロイヤリティーを払うという意識が浸透していないなか、正式な技術移転契約を求めるトヨタは、大量商談を見送ったという経緯もある。しかし、日産、三菱などのメーカーはこの要求を受け入れた結果、各社の主要関連技術が中国全土に広がった。中国はもらったらみんなのものという意識が強いところだが、今日の中国の自動車産業の大きな部品供給力を持つひとつの背景にもなった。
当時のピークの、1985年には、完成車の輸入台数が25万台に達し、そのうちのトヨタは10万台を占めるに至っていた。そしてそのころ、「技貿結合」と称して、外貨不足と技術移転を急ぐという理由から、主に日本メーカーに対して、中国に技術の無償導入を求めてきた。いわゆる"市場を以て技術を要求する"動きの始まりとなったのである。ただ、当時、車の図面が平気で本屋に売っていたこともあり、技術に対して、ロイヤリティーを払うという意識が浸透していないなか、正式な技術移転契約を求めるトヨタは、大量商談を見送ったという経緯もある。しかし、日産、三菱などのメーカーはこの要求を受け入れた結果、各社の主要関連技術が中国全土に広がった。中国はもらったらみんなのものという意識が強いところだが、今日の中国の自動車産業の大きな部品供給力を持つひとつの背景にもなった。
90年代半ば、中国の自動車産業政策には致命的な欠陥があると、国内外で言われていた。それは、政策自身が生産規模優先の考え方で、市場の育成や販売流通政策が大きく欠落していることだった。需要とかけ離れた過剰生産が進んだ。2001年のWTO加盟を経て、これまでの反省から、「自動車市場の拡大なくして自動車産業の発展はない」という認識となり、国家計画委員会中心に自動車の消費促進政策の制定が企画され始めた。この動きにより、エンジンなどの重要部品は、100%外資独資が認められることになり、部品メーカーの進出にも拍車がかかったことで、市場拡大の供給面からの大きなサポートとなっていった。
【杉本 尚丈】
*記事へのご意見はこちら