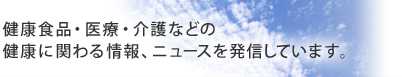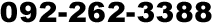健康ビジネスのキー・パーソン(6)~全日本健康自然食品協会 理事長 杢谷正樹氏(3)
お客さまの喜びを肌感覚で共有

私の実家は家業として醤油屋を営んでおり、私が小学校から中学校の頃までは、私の父親は革靴もはいておらず、ネクタイもしていませんでした。一方、友達の父親はネクタイを結んで革靴を履いてバリッとして通勤しているわけです。友達の「とうちゃん」はカッコいいのに、自分の「とうちゃん」は運動靴を履いて前掛けをしている。恥ずかしいと思いました。
よその子の家に遊びに行くと、玄関があって、応接室があって、背広を着ている「とうちゃん」がいて――と、そういうのを見ると羨ましかったです。それでも、家業としての職業観が染み付いていますから、中学校の終わりくらいから、「オヤジの仕事がいいなあ」となんとなく思ったのでしょうね。食べ物を提供して、ときどきおいしかったとか、うまかったとかお客さんに言われるのですよ。そのようなとき、「おおこれか!」と漠然とした感動を覚えたものです。
それでも一方では、サラリーマンの「とうちゃん」たちをカッコイイとは思っているのですけれど、オヤジの配達について行くと、配達先で西瓜や葡萄をくれたり、そこの家の人から「もう10年も20年も、あんたのところの醤油を使わせてもらっているよ」みたいなことを言われると、オヤジがなんとなく喜んでいるような気がしたものです。そういう感じをぼんやりと肌感覚で感じ取っていたのだと思います。
当時は農協の指定醤油屋もやっていました。手伝いの私は、一升瓶を片手に一本持つのがせいぜいだったのに、父親は片手にたくさんぶらさげていくわけです。そういうものを傍目に見ながら、子どもながらに感じるものがありました。だからこそ今、仕事を継いでいるのではないでしょうか。そのあたりの微妙な機微を、今の世代はうまく伝えることができなくなったのではないでしょうか。
【文・構成:田代 宏】
- 表示規制の狭間で揺れる健康食品(5)~表示にすがる健食の功罪(中)「シャンピニオンエキス(1)」
- 【2010年4月13日 10:56】
- ビタミンのはなし(11)~ビタミンEの抗酸化作用
- 【2010年4月13日 08:00】
- 表示規制の狭間で揺れる健康食品(5)~表示にすがる健食の功罪(上)「長命草」
- 【2010年4月12日 11:29】
- ビタミンのはなし(10)~葉酸と新生児の神経管閉鎖障害
- 【2010年4月 7日 08:00】
- ゼロからのスタート!~白川式通販ビジネス講座Vol.1(入門編1)
- 【2010年4月 6日 11:27】
- 食品表示のプロが見分ける健康食品(2)~健康機能の根拠を確認しよう(下)
- 【2010年4月 5日 08:00】
- 食品表示のプロが見分ける健康食品(2)~健康機能の根拠を確認しよう(中)
- 【2010年4月 2日 08:00】
- 食品表示のプロが見分ける健康食品(2)~健康機能の根拠を確認しよう(上)
- 【2010年4月 1日 08:00】
- ビタミンのはなし(9)~ビオチンと掌蹠膿疱(しょうせきのうほう)症や糖尿病
- 【2010年3月29日 08:00】
- 話題の通販メーカー・沖縄教育出版の「和道経営」に学ぶ(下)
- 【2010年3月25日 08:00】
- 話題の通販メーカー・沖縄教育出版の「和道経営」に学ぶ(中)
- 【2010年3月24日 12:13】
- 話題の通販メーカー・沖縄教育出版の「和道経営」に学ぶ(上)
- 【2010年3月23日 13:11】
- ビタミンのはなし(8)~ビタミンAとカロテンの様々な役割
- 【2010年3月23日 10:57】
- ビタミンのはなし(7)~ビタミンAとカロテンの発見と構造決定
- 【2010年3月15日 15:00】
- データマックス、個別相談会付き通信販売セミナー開催!
- 【2010年3月15日 11:44】
- ビタミンのはなし(6)~ビタミンCと血圧調整等の有用性
- 【2010年3月 8日 10:15】
- 山東昭子参議院副議長が国民に檄!「日本食に誇りを」
- 【2010年3月 5日 10:47】
- 長崎大学副学長・中島博士「健康食品はあくまで食品」
- 【2010年3月 5日 09:26】
- 食品表示のプロが見分ける健康食品(1)~健康にいい商品は表示を見て会社で選ぶ(下)
- 【2010年3月 4日 08:00】
- 食品表示のプロが見分ける健康食品(1)~健康にいい商品は表示を見て会社で選ぶ(中)
- 【2010年3月 3日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(7)~エバーライフの元マーケティング本部長がホンネで語る(3)
- 【2010年3月 3日 08:00】
- 食品表示のプロが見分ける健康食品(1)~健康にいい商品は表示を見て会社で選ぶ(上)
- 【2010年3月 2日 13:25】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(7)~エバーライフの元マーケティング本部長がホンネで語る(2)
- 【2010年3月 2日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(7)~エバーライフの元マーケティング本部長がホンネで語る(1)
- 【2010年3月 1日 14:04】
- ビタミンのはなし(5)~ビタミンCとライナス・ポーリング
- 【2010年3月 1日 10:16】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(6)~全日本健康自然食品協会 理事長 杢谷正樹氏(5)
- 【2010年2月26日 15:32】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(6)~全日本健康自然食品協会 理事長 杢谷正樹氏(4)
- 【2010年2月25日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(6)~全日本健康自然食品協会 理事長 杢谷正樹氏(3)
- 【2010年2月24日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(6)~全日本健康自然食品協会 理事長 杢谷正樹氏(2)
- 【2010年2月23日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(6)~全日本健康自然食品協会 理事長 杢谷正樹氏(1)
- 【2010年2月22日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(5)~(株)四方事務所 代表 白川博司氏(3)
- 【2010年2月17日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(5)~(株)四方事務所 代表 白川博司氏(2)
- 【2010年2月16日 09:53】
- ビタミンのはなし(4)-ビタミンCの発見と合成
- 【2010年2月16日 09:52】
- ビタミンのはなし(3)~伊藤 仁
- 【2010年2月15日 09:21】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(5)~(株)四方事務所 代表 白川博司氏(1)
- 【2010年2月15日 09:19】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(4)~林兼産業(株)機能性食品部部長 清木雅雄氏(3)
- 【2010年2月12日 10:53】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(4)~林兼産業(株)機能性食品部部長 清木雅雄氏(2)
- 【2010年2月10日 10:07】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(4)~林兼産業(株)機能性食品部部長 清木雅雄氏(1)
- 【2010年2月 9日 15:30】
- ビタミンのはなし(2)~伊藤 仁
- 【2010年2月 8日 10:18】
- ビタミンのはなし(1)~伊藤 仁
- 【2010年2月 1日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(3)~(株)青い海 代表取締役社長 又吉元栄氏(4)
- 【2010年1月29日 07:56】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(3)~(株)青い海 代表取締役社長 又吉元栄氏(3)
- 【2010年1月28日 07:55】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(3)~(株)青い海 代表取締役社長 又吉元栄氏(2)
- 【2010年1月27日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(3)~(株)青い海 代表取締役社長 又吉元栄氏(1)
- 【2010年1月26日 16:54】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(2)~(株)ケアリング 代表取締役CEO 中尾光明氏(4)
- 【2010年1月21日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(2)~(株)ケアリング 代表取締役CEO 中尾光明氏(3)
- 【2010年1月20日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(2)~(株)ケアリング 代表取締役CEO 中尾光明氏(2)
- 【2010年1月19日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン(2)~(株)ケアリング 代表取締役CEO 中尾光明氏(1)
- 【2010年1月18日 12:58】
- 健康ビジネスのキー・パーソン~エス・エフ・シーグループ 代表取締役会長 島田 修 氏(4)
- 【2010年1月15日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン~エス・エフ・シーグループ 代表取締役会長 島田 修 氏(3)
- 【2010年1月14日 08:00】
- 健康ビジネスのキー・パーソン~エス・エフ・シーグループ 代表取締役会長 島田 修 氏(2)
- 【2010年1月13日 08:00】
- [新連載]健康ビジネスのキー・パーソン~エス・エフ・シーグループ 代表取締役会長 島田 修 氏(1)
- 【2010年1月12日 16:06】