大学時代の友人Fは、在学中から群を抜いて頭が良く、統率力に長けていた。結核を患って3年ほど休学したという話だが、大学闘争時も執行部の中枢(武闘派ではない)として各派をまとめ、同学年の間ではFの右に出る者は皆無だった。卒業後、関西に本社のある地図の会社S社に入社。組合をつくり目障りな課長を降格に追い込み、自らが課長の椅子へ。その直後、組合を潰した。Fの辣腕ぶりに会社首脳部の評判はうなぎ登り。数々の商品を世に送り、業績は急上昇。またたく間にナンバー3にまで上り詰めた。これがFの悲劇の始まりだった。
村議会の大反対を押し切って建て、成功に導く
富弘美術館は大反対を押し切って建てられたという経緯がある。この建物は、ときの総理大臣・竹下登のもとで考案された「ふるさと創生事業」によるものである。当時の村長・尾池善衛門は、「1人の画家のために贅沢」「村民全体に寄与する使い道を」という村民からも村議会からも挙がる反対の大合唱を押し切って建設までこぎ着けた。「観る人に希望を与える彼の美術館を建てるということは、東村だけの問題じゃないと思いました」と語った。
入館者は尾池の目論見通り確実に増えた。とくに1994年7月に皇太子(現・天皇陛下)ご夫妻が来館されて以降、急激に増えた。もはや尾池を非難する村民はいなくなった。「富弘美術館を囲む会」というボランティア団体が各地に誕生。詩画展(一部の詩画と書籍の展示即売会)はボランティアの手によって全国で開催された。それを観た人たちが富弘美術館に来る。さらに口コミがその輪を広げる。「ここに来れば本物が観られるんですよ。それも、全部東村の草花をですね。東村の、です」と取材時村長だった小林宗平氏が胸を張る。
2階ロビーでは星野さんを取材したVTRがエンドレスに流れている。作品を制作中の星野さんと夫人の昌子さんの様子が映し出されている。ベッドに横になり、ガーゼに巻いた絵筆を口にくわえた星野さんが、妻に色を混ぜ合わせるように指示を出している。「オレンジと紫をちょっと…」。妻が筆を洗い、オレンジと紫色を筆の先につけて混ぜ合わせ、紙に試し塗りをして夫に見せる。「…いいよ」「はい」。再び描き出す。しばらくして、「うん。いいね。Vサインだ」。夫婦の笑顔。「1人では絶対に描けない。妻と母が協力してくれる。それで初めて描ける。描きあげたものを、妻がほめてくれたり、母が驚いてくれたりするのが、次の原動力になっているんですね」とナレーションが流れた。
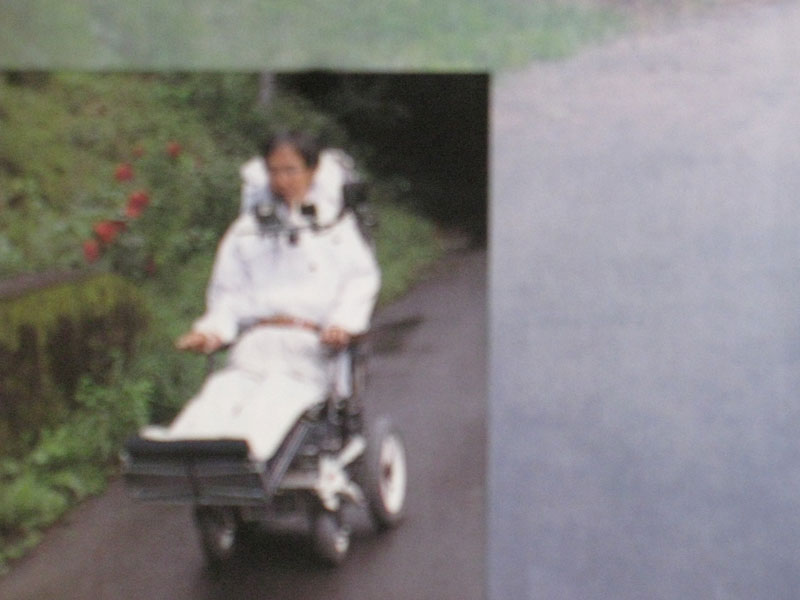
(筆者撮影)
富弘美術館を再訪したとき、館長・金子光一氏に、「星野さんの散歩道というのがあって、そろそろ散歩の時間になります。体調のいいときに限られますが…」と教えられた。鬱蒼と生い茂った山道を歩いていると、偶然にも星野さんに遭遇。運が良かった。特注の電動車椅子に乗り、白い散歩服に身を包んだ星野さんが、細い坂道を時速4㎞のスピードでのんびりと下りてくる。事情を説明し、館長から教えられたと告げると、しょうがないなあ、という顔をしながらも一緒に散歩することに同意してくれた。散歩道と時間が知れてしまえば、ファンが押し寄せてくるのは必定。場所も時間も口外しないという約束だ。星野さんの散歩道は、山吹色した収穫前の稲に囲まれるようにして延びている。アキアカネが少し暗くなりかけた空を舞っていた。チリン、と鈴の音がした。アスファルトが少し窪んでいるのだろう。警戒音に聞こえた。
急な坂道は車椅子を逆にし、後ろ向きで上るという。そのほうがバランスがとれるからだ。実際に逆向きで走ってくれた。その笑い顔がどこか少年のようなあどけなさを感じさせた。バックミラーを見ながら操縦する。その操縦も顎でする。実にスムーズに走行する。私には高度なテクニックを駆使しているように見えるが、顎での操縦を習得してしまった星野さんには、朝飯前のことなのだろう。いろいろな話をした。大笑いの楽しい散歩になった。
そのまま自宅に案内された。昌子夫人手づくりのクッキーと温かいコーヒーでもてなされた。私はそれを庭にある石のテーブルでいただいた。星野さんは車椅子のまま昌子さんの手から直接食べた。障害を持つ人、それを支える人たち。その両方の計り知れない苦労があるはずなのに、西の空が茜色に染まりかけた風景のなかでは霧消していく気がした。
星野富弘さんは今年4月28日、呼吸不全のため78歳で亡くなった。5月10日から19日まで、東京都江東区の高齢者福祉施設「故郷の家・東京」で個展が開かれた。突然の訃報を受け、「追悼展」となり、多くのファンが詰めかけた。以降、「富弘美術館を囲む会」のボランティアメンバーが各地で「追悼展」を開くことになるのだろう。
 一方、Fは役員会の緊急動議により罷免された。Fは会社を急成長させ、絶大な人気と権力を握った。それを会社の創業家が、このままでは自分の息子たちをトップに据えることが不可能だと判断したのだろう。関西の小さな出版社を一社員の手で急成長させた。会社としては願ってもないことなのだろうが、自分の身内が可愛い創業家にとってFの存在そのものが疎ましくなったのだ。Fは10年ほど前に他界した。亡くなる数日前、病院に見舞いに行った。Fの目はうつろだったが、指し出した手を力強く握り返してくれた。私を認識してくれたのだと思う。出る釘は打たれるというが、こうして優秀な社員を潰していく成り上がりの会社が日本にはまだ存在する。情けない限りだ。
一方、Fは役員会の緊急動議により罷免された。Fは会社を急成長させ、絶大な人気と権力を握った。それを会社の創業家が、このままでは自分の息子たちをトップに据えることが不可能だと判断したのだろう。関西の小さな出版社を一社員の手で急成長させた。会社としては願ってもないことなのだろうが、自分の身内が可愛い創業家にとってFの存在そのものが疎ましくなったのだ。Fは10年ほど前に他界した。亡くなる数日前、病院に見舞いに行った。Fの目はうつろだったが、指し出した手を力強く握り返してくれた。私を認識してくれたのだと思う。出る釘は打たれるというが、こうして優秀な社員を潰していく成り上がりの会社が日本にはまだ存在する。情けない限りだ。
(つづく)
<プロフィール>
大山眞人(おおやま まひと)
 1944年山形市生まれ。早大卒。出版社勤務の後、ノンフィクション作家。主な著作に、『S病院老人病棟の仲間たち』『取締役宝くじ部長』(文藝春秋)『老いてこそ2人で生きたい』『夢のある「終の棲家」を作りたい』(大和書房)『退学者ゼロ高校 須郷昌徳の「これが教育たい!」』(河出書房新社)『克って勝つー田村亮子を育てた男』(自由現代社)『取締役総務部長 奈良坂龍平』(讀賣新聞社)『悪徳商法』(文春新書)『団地が死んでいく』(平凡社新書)『騙されたがる人たち』(講談社)『親を棄てる子どもたち 新しい「姥捨山」のかたちを求めて』『「陸軍分列行進曲」とふたつの「君が代」』『瞽女の世界を旅する』(平凡社新書)など。
1944年山形市生まれ。早大卒。出版社勤務の後、ノンフィクション作家。主な著作に、『S病院老人病棟の仲間たち』『取締役宝くじ部長』(文藝春秋)『老いてこそ2人で生きたい』『夢のある「終の棲家」を作りたい』(大和書房)『退学者ゼロ高校 須郷昌徳の「これが教育たい!」』(河出書房新社)『克って勝つー田村亮子を育てた男』(自由現代社)『取締役総務部長 奈良坂龍平』(讀賣新聞社)『悪徳商法』(文春新書)『団地が死んでいく』(平凡社新書)『騙されたがる人たち』(講談社)『親を棄てる子どもたち 新しい「姥捨山」のかたちを求めて』『「陸軍分列行進曲」とふたつの「君が代」』『瞽女の世界を旅する』(平凡社新書)など。




























