【特別寄稿】ウクライナ紛争──勝敗を決める原理~西洋社会の内部崩壊と集団信仰の喪失~
京都精華大学 准教授 白井聡 氏
ウクライナ紛争における西側諸国の敗北でいよいよ明らかになりつつある西洋世界の崩壊を、エマニュエル・トッドの『西洋の敗北』を基に、宗教的・社会的規範の喪失による西洋社会の内部崩壊として読み解き、日本社会にも規律崩壊をもたらしている原因を明らかにする。
日本を含む西側の敗北
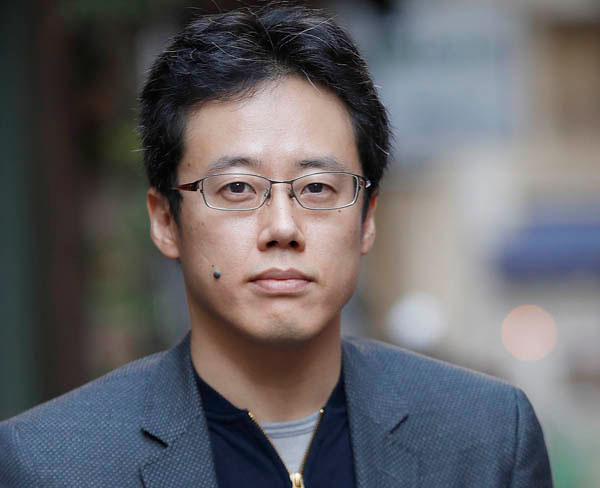
白井聡 氏
先に筆者は、2022年のロシア・ウクライナ紛争勃発以降の世界の情勢を「グローバル南北戦争」として描き出した。長引いているこの紛争は、ロシアとウクライナというスラヴ民族同士の小競り合いなどではなく、ロシアvs NATO、ロシアとその友好国vsアメリカ合衆国とその同盟国、さらには「ロシアを筆頭とするグローバル・サウス勢力」vs「先進諸国」の紛争であるとの構図を露わにしている。
注目されるべきは当然、その帰趨である。この紛争にどちらが勝利を収めるのか。ウクライナ紛争そのものの勝敗は、大方見通しが立ちつつある。開戦直後に「専門家」たちが述べた見解と現実は大きく異なり、ロシア経済は崩壊せず、プーチン体制の崩壊も起こらず、軍事的勝利はロシアのものとなる情勢にある。ゼレンスキー・ウクライナ大統領も最近では停戦の条件について頻繁に言及しており、幕引きを模索している。
この戦争にロシアが勝ち、ウクライナが敗れるのだとすれば、敗れるのはウクライナ一国ではない。一部の領土の喪失や多数の死傷者、破壊され荒廃した国土というわかりやすい敗戦の傷がなくとも、その敗北はNATO諸国、アメリカとその同盟者、そしていわゆる西側世界=先進諸国すべてにとっての敗北であるはずなのだ。この敗北は何を意味するのか。そしてなぜ、西側諸国は負けつつあるのか、より端的にいえば、この日本も西側諸国の一角であるという自己認識を有しているのだから、なぜ我々は負けつつあるのか。
これらの問いに対して回答を与えようとする興味深い試みを提出しているのが、フランスの人類学者、エマニュエル・トッドの最新作、『西洋の敗北』(文藝春秋、2024年)である。同書を参照しながら、この戦争の意味、そしてこの戦争における敗者が西洋世界であるのならば、その敗北の由来と含意を考察してみたい。
崩壊する西洋世界
『西洋の敗北』では多岐にわたるテーマが言及されており、それぞれが極めて興味深いものであるのだが、本稿では、トッドの見方の最大の特徴、すなわちこの敗北の原因を強大なロシアによってもたらされたというよりも、西洋世界の自滅・自壊に求めているところに注目したい。自滅しつつある西洋世界の先導役は、いうまでもなくアメリカであり、第二のプレイヤーは欧州である。
近代世界を支配してきた欧米=西洋の原理が衰弱し、ニヒリズムが猖獗することにより、ロシアとの戦いが起こる以前に、欧米世界は内部崩壊しつつあったのであり、ロシアとの戦いとそこにおける敗北は、この内部崩壊を表面化させたにすぎない、とトッドは見ている。
西側の内部崩壊とは、すでに数多の論客によって指摘されてきたことだが、「歴史の終わり」(フランシス・フクヤマ)により最終的な勝利者となったはずの自由民主主義と資本主義市場経済を基盤とする先進諸国の社会が、軒並み脱出口の見えない混乱に陥っている事態を指している。その代表がアメリカだ。
拡大し続ける階級格差、ポスト・トゥルース(※1)に乗っ取られた民主主義、人種差別感情の高揚、価値観の和解不可能までの分断といった現象がしばしば挙げられるわけだが、トッドは近年見られる乳幼児死亡率の上昇や白人低学歴男性における寿命の縮小といった、端的に命に関わる数値を重視する。
これらの数値は、貧困による医療資源へのアクセスの困難や、絶望の果ての薬物乱用やアルコール依存症による短命化を物語っており、文字通りのアノミー(社会の無規範化、社会の崩壊)を指し示すものだからである。日本でも会田弘継らが指摘するように、ドナルド・トランプの二度にわたる大統領就任は、アメリカの衰退と混乱の原因ではなく、結果にほかならない。
そして、トッドの見るところ、ヨーロッパの中心国もアメリカと五十歩百歩の状況にある。ドイツ・フランス・イギリスでは、そろって既成政党の統治能力が空洞化しており、政治的混乱が続き、内閣の交替が相次いでいる。
ウクライナ紛争により崩壊したのは、ロシアの政権ではなくこれらの国々の政権であったことは、壮大な皮肉であるというほかない。そこでは既成政党を「右翼ポピュリズム」が脅かしている、と我々は散々聞かされているが、ここでもまた病理として名指しされたものは、病理の原因ではなく結果であろう。
脱宗教化と国家の崩壊
では、西洋社会の崩壊は、端的に言って何に根差すのか。トッドが重要視しているのは、宗教の要素である。現代において、キリスト教圏の先進諸国で一層の宗教離れが進んできた―日本も同様である──のは周知の事実だ。このような現代の宗教離れがアノミー(※2)を生じさせている、という単純な見方をトッドは採らない。そもそも世俗化は西洋近代の全般的傾向であり、いまに始まったことではない。トッドが着目するのは、世俗化=脱宗教化における段階である。
いわく、近代初期の段階から脱宗教化は始まるわけだが、18世紀から20世紀にかけての時代においては国民国家を基盤とする諸々の政治的イデオロギーがキリスト教信仰の代替物として、集団的信仰の対象として機能したのである、と(※3) 。つまり、宗教そのものは廃れたが、疑似宗教がその代わりの機能をはたした。
具体的にいえば、教会に通う人々が少なくなったとしても、たとえば、ナショナリズムに基づく同胞感情により、平等で包摂的な福祉国家を求めるといった感情が広く共有された。あるいは、プロテスタンティズムの信仰を明確にはもはや持っていないとしても、勤勉さや労働規律といった規範を遵守する精神が保持される、といったことである。
そして、おおよそ20世紀末ごろから、宗教から受け継がれた慣習と価値観が消滅し始めた、とトッドは論じる。「すると、ようやく今私たちが生きている状態が出現する。代替となるいかなる集団的信仰も失った個人からなる宗教の絶対的虚無状態である」(※4)。それは、グローバル化=国民国家の解体の結果であるか、あるいは原因であると見ることもできよう。いずれにせよ、トッドが深く確信するのは、いかなる社会も何らかの集団的信仰なしには体を成さず持続不可能である、ということだ。
かくして、トッドが突きつける現代西洋社会についての診断は、それぞれの国が国民を束ねる統合原理をもはや欠いており、国家として内的に崩壊している、というものだ。いかなる統合原理ももたない社会とは、ニヒリズムに覆われた社会であり、社会であることをやめた社会である。またそのとき、その国家に国民は実質的にはいなくなる。
個人の解放と社会の空洞化

他方、個人の側に目を向ければ、宗教の後退は「個人の解放」をもたらしたが、解放されたはずの個人は「いかなる集団的信仰も失った個人」へといつの間にか変質した。日本でよく口にされる「行き過ぎた個人主義」という決まり文句は曖昧だが、もともとは個人を解放するはずだった原理が、個人を孤立させ社会的にはアノミーを生み、苦悩をもたらすようになってしまったことを、直感的に言い当ててはいる。
トッドの見るところ、問題は個人の内面的次元にとどまらず、極めて具体的な帰結を生む。社会のアノミー状態は、西洋世界の実体経済レベルでの弱体化、すなわちエンジニアリング部門からの人材逃避と産業の空洞化をもたらした。地道な努力により技術開発に取り組むよりも、肥大化した金融産業で利益を追求する方が、いかなる集団的信仰ももたない個人にとっては合理的な選択である。
ここでもアメリカがその典型をなしているが、こうした経済構造により、製造業は衰退し、軍事技術においてもはるかに防衛費の水準が低いはずのロシアに、いくつかの分野で後塵を拝することになっている。つまり、アノミーはウクライナ紛争における敗北に直接つながっている、とトッドは考えるのである。
トランプ政権の課題「アメリカ」は復活するか
こうした状況下で大統領として再登板するトランプは、アノミーからアメリカ社会を救い出すことができるのか。トランプはたしかに、没落した労働者階級への共感を表明し、彼らの怒りを代弁し、グローバル化の真逆を行く関税政策によってアメリカの製造業を復活させる、と約束している。
もちろん、その履行可能性は不透明だ。圧倒的な工業力によって第二次世界大戦に勝利して覇権国となったアメリカが、製造業を空洞化させて「世界の工場」の役割を東アジア地域の諸国に譲り渡し、自らは金融資本主義に依存するようになってすでに久しいからである。
とはいえ、興味深いのは、副大統領に就任予定でトランプ以後の大統領候補であるとも目されているJ.D.ヴァンスの姿勢である。ヴァンスは没落してアノミー状態に陥った労働者階級の家に生まれ、海兵隊での勤務を経て、大学進学のチャンスを摑み取って這い上がった。
その経験を書いた『ヒルビリー・エレジー』の著者として有名になり、副大統領の地位にまで上昇してきた人物である。その著書で主張していることはまさに、エートス(※5)の復権である。民主党の体現してきたリベラリズムが、社会的弱者に対して福祉を与えることはできても、尊厳を与えることはできなかったことを批判し、人々の自助努力による尊厳の回復を説いている。
ただし、この考え方の方向性が正しいとしても、自助努力による尊厳の回復が可能な産業構造の再建がはたして可能であるのか否か。それができなければ、「集団的信仰」、すなわち人々に共有される「アメリカとは何か」という信念の復活は起こり得ず、従っていま崩壊状態にある社会の再建も達成できないであろう。
ロシアの「信仰」戦略 日本社会の課題
他方で、軍事的勝利を摑みつつあるロシアが十全に社会たり得ているかどうかもまた定かではない。しかし、プーチンとそのブレーンたちが、国民国家を成り立たしめる「集団的信仰」の必要性に対し、西洋世界の指導者よりもはるかに自覚的であることは疑い得ず、さしあたりいまはそれは軍事的勝利をもたらしている。
以上に論じてきたことは、我々日本人にとってまったく他人事ではないことはすでに明らかであろう。政治的無関心と冷笑癖がはびこる日本社会は、すでにして相当程度にアノミー状態にある。しかし、我々が「集団的信仰」を取り戻すのは実は本来さほど困難ではない。なぜなら、その信仰の内容は、戦後の異様な対米従属からの脱却以外の何物でもないことは、自明であるからだ。
※1 客観的真実性よりも個人の主観的感情や信念が人々の意見に影響力をもつ状況のこと(編注)。 ^
※2 社会の規範が崩壊すること(編注)。 ^
※3 エマニュエル・トッド『西洋の敗北──日本と世界に何が起きるのか』大野舞訳、文藝春秋、2024年、167頁。 ^
※4 エマニュエル・トッド『西洋の敗北──日本と世界に何が起きるのか』大野舞訳、文藝春秋、2024年、169頁。 ^
※5 人間が獲得する習慣、倫理性のこと(編注)。 ^
<プロフィール>
白井聡(しらい・さとし)
政治学、社会思想研究者。東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。一橋大学大学院社会学研究科総合社会科学専攻博士後期課程単位修得退学。博士(社会学)。主にロシア革命の指導者であるレーニンの政治思想をテーマとした研究を手がけてきたが、3.11を起点に日本現代史を論じた「永続敗戦論—戦後日本の核心」(太田出版)により、第4回いける本大賞、第35回石橋湛山賞、第12回角川財団学芸賞を受賞。著書に「国体論」(集英社新書、2018年)、「武器としての『資本論』」(東洋経済新報社、2020年)、「未完のレーニン」(講談社学術文庫、2021年)ほか。




























