【特別寄稿】SNSがシルバー民主主義を破壊して政治が衆愚化する~時代遅れの公選法では民主主義は守れない~
(株)アゴラ研究所 所長 池田信夫 氏
2024年は、インターネットが選挙を大きく変えた年だった。東京都知事選挙では石丸伸二氏(元安芸高田市長)が165万票を得て第2位になり、兵庫県知事選挙では、県議会に全会一致で不信任された斎藤元彦氏が出直し知事選挙で再選されるという劇的な結果になった。これはいずれもネット選挙の影響と考えられるが、それが望ましい結果をもたらすとは限らない。
未確認情報で二転三転した兵庫県知事選挙
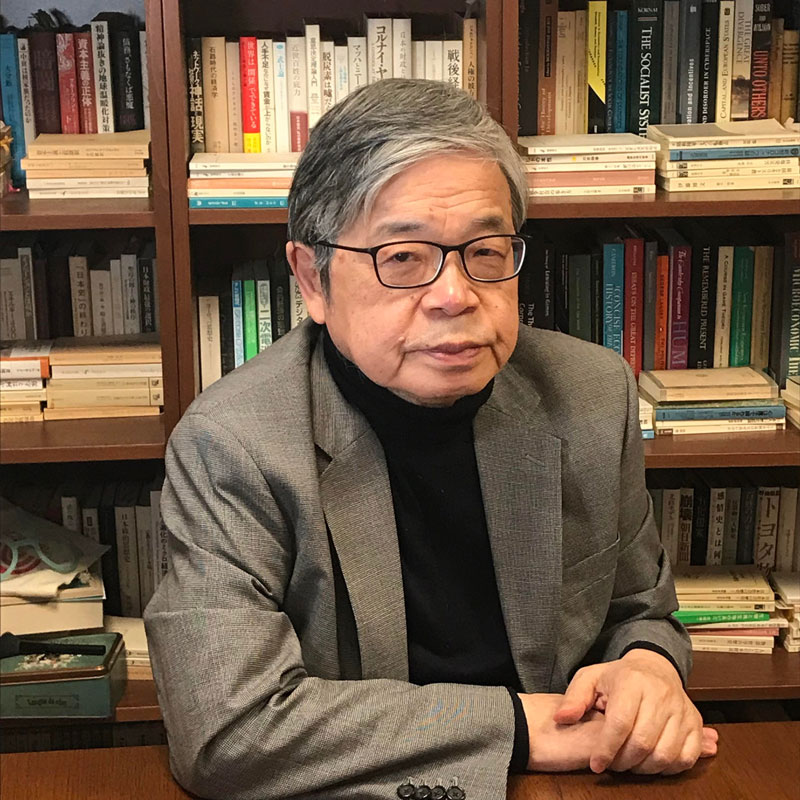
所長 池田信夫 氏
兵庫県知事選挙が全国的な関心事になったのは、元西播磨県民局長が自殺してからだった。ほとんどの人は内部告発した元局長を知事がパワハラで自殺に追い込んだという印象を受け、この問題が県議会で大きく取り上げられたが、詳しくみると因果関係は逆である。
最初は元局長が匿名で知事のパワハラなどについての「告発文」をマスコミに流していたが、内部調査で身元が特定されて県は彼の公用パソコンを押収し、3月末に解任した。これを恨んだ元局長は4月4日に県の公益通報窓口に通報したが、県はその内容について「核心的な部分が事実ではなく、公益通報に該当しない」として停職3カ月の懲戒処分にした。これを県議会が問題にし、百条委員会が開かれることになったが、元局長は百条委員会で証言する直前に自殺した。
つまり彼の自殺の原因は知事のパワハラではなく、百条委員会で公用パソコンの内容について証言することを恐れたためと考えられる。ところが当初から知事のパワハラという線で報道していたマスコミはそのトーンを変えず、議会もそれに乗せられ、百条委員会では知事の違法行為が出てこなかったにもかかわらず、9月に県議会は全会一致で不信任決議し、知事は辞任して出直し選挙が行われた。
これは公平にみて県庁内の泥仕合であり、知事の対応にも問題はあったが、不信任するような違法行為があったわけではない。元局長の内部告発も身元が割れてからであり、公益通報とは言い難い。この背景には、約50年にわたって知事が副知事を後継者に引き上げて県庁内に緊張感がなく、1,000億円かけて豪華な新庁舎を建設する計画など非効率な行政が行われていたのに対して、斎藤知事が綱紀粛正をはかり、出入り業者との癒着を絶ち切ったことに職員が反発した面もあった。
いずれにせよ百条委員会で事実が確認される前に、県議会がマスコミに押されて不信任決議をしたのは拙速だった。それに対して「斎藤知事は無実だ」という論陣を張ったのが、動画やX(旧・ツイッター)などのSNSだった。とくに「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首は知事選挙にみずから立候補して斎藤氏の再選を呼びかけ、「自殺の原因は公用パソコンに記録された不倫日記だ」といった真偽不明の情報をインターネットの動画やXで流した。
これまでの常識では、関西だけでも100万人単位の人が見るテレビと、たかだか数万人が見るだけのSNSでは影響力がケタ違いだが、今回はネットの刺激的な動画が何百万回も再生されてマスコミの情報をくつがえし、斎藤知事が再選された。投票率は2021年の前回選挙に比べて14.55ポイントも上がり、世代別にみると10~30代では斎藤氏に投票した有権者が対立候補の2倍にのぼった。これはネットを見る層ほど斎藤氏に投票したことを示す。
SNSで有権者が大量の多様な情報を得るようになったが、それによって情報の質が上がるとは限らない。とくに問題になった公用パソコンについては、肝心の中身が百条委員会で審議される前に、不倫日記などの未確認情報が流されたため、有権者の関心がそこに集中し、その実態がわからないまま斎藤氏の逆転勝利になった。ネットで真偽不明の情報が拡散されて何が本当かわからなくなり、衆愚政治化が進んでいる。
ネット動画が選挙をエンタメにした
 昨年7月に行われた東京都知事選挙でも、石丸伸二氏が元民進党代表で前参議院議員・蓮舫氏を抑えて2位に入る意外な結果になった。世代別にみると、石丸氏も10~20代で1位だった。支持政党別では、無党派層で最大の支持を得た。これまでどの党も取れなかった無党派の若い世代というブルーオーシャンを、彼が初めて取ったのだ。
昨年7月に行われた東京都知事選挙でも、石丸伸二氏が元民進党代表で前参議院議員・蓮舫氏を抑えて2位に入る意外な結果になった。世代別にみると、石丸氏も10~20代で1位だった。支持政党別では、無党派層で最大の支持を得た。これまでどの党も取れなかった無党派の若い世代というブルーオーシャンを、彼が初めて取ったのだ。
それは石丸氏が政治家として優れていたからでもなければ、その政策が魅力的だったからでもない。むしろ彼の嫌う「政治屋」としてのテクニックが傑出していたからだ。この点は彼の選挙参謀だった藤川晋之助氏の分析が的確である。
(石丸氏は)街頭演説を200回超やったが、特徴的なのは、細かい政策をまったく言わないことだった。自己紹介を言い続けた。「小さな問題はどうでもいいんだ」といって「政治を正すんだ」という話をずっとやり続けた。それでも来る人の8、9割は「すごい」と言って帰っていく。
大衆のほとんどは政策を理解していないし興味もない。景気が悪いのはデフレのせいだとか消費税が悪いぐらいにしか考えていないので、難しい政策を説明しても、ほとんどの人にはわからない。それより「皆さんの生活が苦しいのは小池都政のせいだ」と動画で繰り返し、「自分なら変えられる」といえばいいのだ。
そのメディアの主役が、今やテレビから動画になった。石丸氏は安芸高田市長のころから、市議会で市議を面罵するショート動画をYouTubeやTikTokで拡散し、総インプレッションは1億回を超えた。都知事選でも演説の動画を他の人が切り抜いて流すことを容認し、切り抜き動画で収益化するYouTuberがたくさん生まれた。
今まで政治経済系のコンテンツは、動画には向いていないといわれていた。ビジュアルとしておもしろくないし、理解するには時間がかかるからだ。それが変わり始めたのは「虎ノ門ニュース」や「ニュース女子」などのネトウヨ系の動画だった。中身は幼稚で互いにケンカしたりするが、それがアクセスを集め、1回で数十万アクセスを集めることもある。石丸動画も、政治をエンタメにした。市議会の議場で議員を罵倒する動画が切り取られ、最大100万回再生された。アルバイトを募集してこういう動画を大量にコピーしたのが、都知事選挙で大量得票した原因だった。
政治がエンタメ化するのは、必ずしも悪いことではない。とくにシルバー民主主義で自分の意思は反映されないとあきらめていた若い無党派層が、石丸氏に投票した。これで下がり続けていた都知事選の投票率も5.62ポイントも上がった。しかしその選択が賢明になるかどうかは別の問題である。石丸氏は次の都知事選に向けて準備をしているといわれるが、都民としては御免こうむりたい。
ネット選挙を事実上禁止する公選法
 しかしネット選挙で政治の経験がない素人が参加したため、思わぬトラブルが起こった。斎藤氏の「SNS戦略を企画立案した」というPR会社の社長が、その詳細をブログに書き、「斎藤氏がオフィスにきてSNS戦略を依頼された」と書いた。このPR会社は斎藤氏から約70万円の支払いを受けていたため、選挙違反ではないかという批判が出た。
しかしネット選挙で政治の経験がない素人が参加したため、思わぬトラブルが起こった。斎藤氏の「SNS戦略を企画立案した」というPR会社の社長が、その詳細をブログに書き、「斎藤氏がオフィスにきてSNS戦略を依頼された」と書いた。このPR会社は斎藤氏から約70万円の支払いを受けていたため、選挙違反ではないかという批判が出た。
斎藤氏側は「SNS戦略の企画立案などについて依頼をした事実はない」と反論したが、PR会社のブログは斎藤氏との打ち合わせの写真や10月から11月17日(投票日)までのスケジュールを示し、「広報全般を任せていただくことになりました」と書いていた(後に削除)。
公職選挙法では、有償で選挙運動を行うことは違法で、その例外としてポスターやチラシなどの印刷代とウグイス嬢や事務処理などの実費は認めている。PR会社の社長は斎藤氏の選挙演説の横でインスタライブを撮影し、Xアカウントで情報発信しており、これは単なる事務とはいえない。それについて斎藤氏が何も依頼していないということも考えられない。
少なくともPR会社が選挙期間中にSNS活動を仕切ったことには疑問の余地がないが、問題はこれが有償で依頼された業務か個人的なボランティアかということである。陣営側は選挙運動の依頼が違法だと認識して請求書の内訳を実費だけにしたと思われるが、PR会社は違法性をまったく意識せず、広報活動(選挙運動)を任されたと明言していた。この事件については兵庫県警と神戸地検に告発状が出され、まだ起訴されるかどうかはわからないが、この認識の齟齬が争点になろう。
根本的な問題は「当選を得もしくは得しめまたは得しめない目的をもつて選挙人または選挙運動者に対し金銭の供与」をしたときは、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処するという公選法221条1項の規定が、有償の選挙運動を禁止していることだ。選挙はボランティアでやらなくてはならず、選挙運動にカネを払うと買収になる。
ポスターの印刷などの実費以外は選挙運動なので、業者が候補からカネを受け取ってはならない。電話やハガキはかまわないが、電子メールは禁止である。ホームページの更新は許されるが、新たにデザインすることはできない。動画の投稿もすべて無償でやらなければならない。23年の江東区長選挙では、柿沢未途衆議院議員(当時)がYouTubeの動画を280万円で業者に依頼したことが違法とされ、彼は議員辞職した。紙のポスターの印刷費は認められるのに、動画やウェブサイトの制作費が認められないのはおかしい。
これは選挙運動にカネを出すのはすべて買収にあたるという公選法の原則によるものだが、今どき浮世離れした原則である。見返りなしで2週間以上、ボランティアで選挙運動してくれるのは、よほど暇な人だけだろう。広告代理店や選挙コンサルなどは、規制をかいくぐるために別の団体をつくるなどのテクニックを知っているが、素人は引っかかってしまう。
実質的な参入障壁 現職を守る公職選挙法
有償の選挙運動を認めると金で票を買えるという反論があるが、法定選挙費用は決まっているので、その範囲内なら買収だろうが戸別訪問だろうが何をやってもかまわないはずだ。法定選挙費用に抜け穴が多いので、香典や祭の寄付など個別の用途が違法とされるのだ。
公選法には、この他にも常識はずれの細かい禁止規定が山のようにある。その罰則が(執行猶予でも)当選無効と重いので、素人に広報活動を仕切らせるのは自殺行為である。このような違反事件は地方選挙では日常的に起こっており、落とし穴だらけの公選法は、現職を守る参入障壁になっているのだ。
ネット選挙は本格的に始まったばかりで、それがどれほど政治に影響をおよぼすか、また政治の質が向上するのかどうかはわからない。今のところ未確認情報に若い有権者が飛びついて衆愚化する恐れも強い。警戒を強めた政府はSNSの規制を検討しているが、これほど大量の情報を政府が規制することは不可能である。それよりネット時代に適応しない公選法の規制を改革し、SNSが民意を正しく反映する制度設計を考えるべきだ。
<プロフィール>
1953年生まれ。東京大学経済学部卒業。NHK職員として報道番組の制作を経て、国際大学GLOCOM教授、(独)経済産業研究所上席研究員などを経て、(株)アゴラ研究所代表取締役所長。



























