リペア社会へのシナリオ(後編)~街を修理する準備はできているか~(1)
 日本の技術者は、“街のカタチ“をアップデートすることに目を向けなければならない。気候変動にともなう洪水、豪雨、海水面の上昇、道路の浸水、熱波、山火事に備え、建築家やエンジニア、都市計画家は、それに耐えられる建物、街、環境の設計、そして、そろそろ都市インフラの再構築をしなければならなくなっている。
日本の技術者は、“街のカタチ“をアップデートすることに目を向けなければならない。気候変動にともなう洪水、豪雨、海水面の上昇、道路の浸水、熱波、山火事に備え、建築家やエンジニア、都市計画家は、それに耐えられる建物、街、環境の設計、そして、そろそろ都市インフラの再構築をしなければならなくなっている。
日本の“もったいない”
人類が進化するには、長い時間がかかる。最近の学説によれば、アフリカでホモ・サピエンスが誕生したのが15万年前―アフリカから出て世界に広がり始めたのが6万年前、ヨーロッパへたどり着いたのが4万2000年前、オーストラリアへは5万年前、シベリアへは4~5万年前、日本へは3万8000年前だそうだ。つまり、現在とまったく同じような肉体になったのは、せいぜい3万年から5万年前ぐらい。我々は、4万年ほど前の設計図でできた肉体で生きてきている。本来なら体を動かしてドングリを拾い集めたり、弓矢でシカを狩ったりしながら、ギリギリの栄養で生き延びるようにできている体なのに、現代人は歩くのさえ面倒がって自動車に乗り、食べたいだけ食べて肥満に悩んでいる。
私たちの肉体は、その便利さに合うように設計されていない。我々の肉体の設計仕様に近い生活は、せいぜい昭和30年くらいまでの暮らしぶりだろう。それは環境のためでも、地球のためでも、CO2のためでもなく、自分のためだと思う。今のようにすべてを石油任せにし、ほとんど体を動かさず頭も使わず、夜更かしをして生き、何でも消費し尽くしていく状況は、破滅的といっていいほど不自然だと悟るべきだろう。
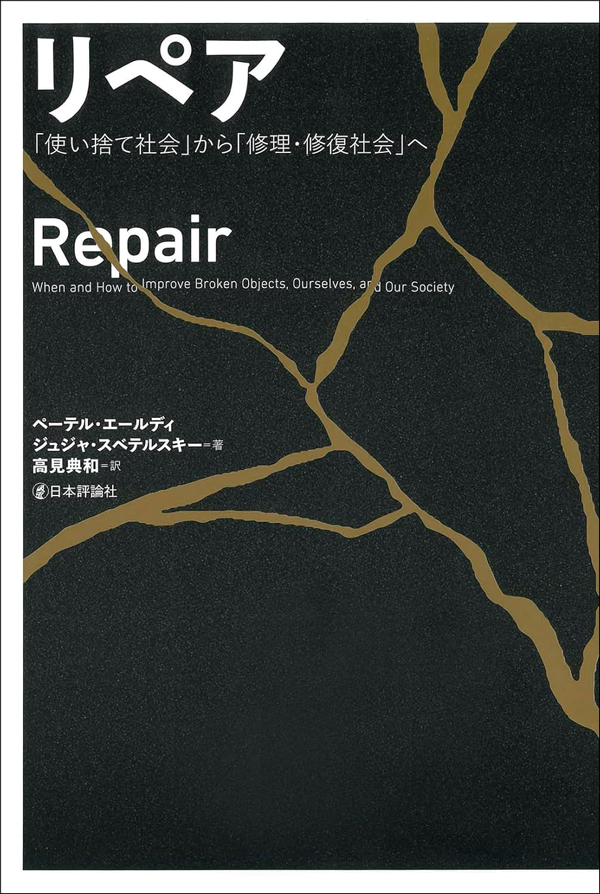
「修理・修復社会」へ 』
西洋文化の影響や高度経済成長により、日本は大量消費の時代へと変貌した。今日ではモノがあふれかえっている日本だが、もともと日本には「もったいない」精神が根付いていた。“MOTTAINAI”は今や世界共通語となっているが、この精神の起源は、江戸時代に遡る(環境省「平成20年版環境白書・循環型社会白書」より)。江戸の都市には1,000以上の組織がリサイクルを生業として働いていたという。
たとえば古着、古傘、古紙などは再利用し、灰は肥料や染料として使われていく仕組みがあった。し尿や生ゴミは肥料として農村に送られ、そこで栽培された野菜が江戸で消費されるという資源循環。壊れたモノは修理し、着物も古着を買い、自分で補修して長く使うことが当たり前の「モノを大切にする習慣」...

月刊まちづくりに記事を書きませんか?
福岡のまちに関すること、建設・不動産業界に関すること、再開発に関することなどをテーマにオリジナル記事を執筆いただける方を募集しております。
記事の内容は、インタビュー、エリア紹介、業界の課題、統計情報の分析などです。詳しくは掲載実績をご参照ください。
記事の企画から取材、写真撮影、執筆までできる方を募集しております。また、こちらから内容をオーダーすることもございます。報酬は別途ご相談。
現在、業界に身を置いている方や趣味で建築、土木、設計、再開発に興味がある方なども大歓迎です。
また、業界経験のある方や研究者の方であれば、例えば下記のような記事企画も募集しております。
・よりよい建物をつくるために不要な法令
・まちの景観を美しくするために必要な規制
・芸術と都市開発の歴史
・日本の土木工事の歴史(連載企画)
ご応募いただける場合は、こちらまで。不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
(返信にお時間いただく可能性がございます)



























