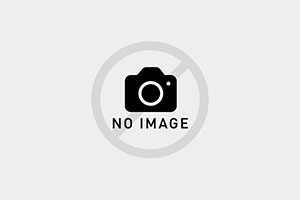この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
 気象庁が「2017(平成29)年7月九州北部豪雨」と名付けた豪雨水害。そのなかで、クローズアップされているのが、無数の流木の存在である。専門家の分析では、「山の地表近くに堆積する「マサ土」(真砂土。花崗岩が風化してできた砂。水はけがよいが、多量の水分を含むと一気に流れ出して土砂崩れを引き起こす)が、今回の豪雨による大量の水を含み、崩壊しやすい状況を作った。その地表に植林されているスギやヒノキは、根が浅く密度が浅い。よって根による保持力が弱く、地表のマサ土とともに樹木が流されてしまった」としている。
気象庁が「2017(平成29)年7月九州北部豪雨」と名付けた豪雨水害。そのなかで、クローズアップされているのが、無数の流木の存在である。専門家の分析では、「山の地表近くに堆積する「マサ土」(真砂土。花崗岩が風化してできた砂。水はけがよいが、多量の水分を含むと一気に流れ出して土砂崩れを引き起こす)が、今回の豪雨による大量の水を含み、崩壊しやすい状況を作った。その地表に植林されているスギやヒノキは、根が浅く密度が浅い。よって根による保持力が弱く、地表のマサ土とともに樹木が流されてしまった」としている。
熊本県内のある森林組合の理事長は、現在の林業について警笛を鳴らしている。「これまで国策としてスギ・ヒノキという針葉樹の植樹を促進してきました。本来なら地形と地盤そして土質を詳細に調査した上で、針葉樹に適しているかいないかを判断して植えるのです。しかし、残念ながら針葉樹に適さない山林にもスギ・ヒノキが植えられているのが現状で、今回の九州北部豪雨のような事態を引き起こしてしまいました。今回のような被害は、これから全国どこでも発生する可能性があり、今すぐ治水対策や林業の改革を行うべきです」として、国と林業界が一体となって取り組むべきだとしている。それは山を自然に戻すことで、キーファクターはかつて日本の山の多くで枝を広げていた「広葉樹」であるという。
【河原 清明】
関連キーワード
関連記事
2026年2月12日 13:00
2026年2月9日 13:00
2026年1月30日 17:00
2026年1月21日 13:00
2026年1月20日 17:20
2025年12月5日 14:30
2026年2月7日 10:30