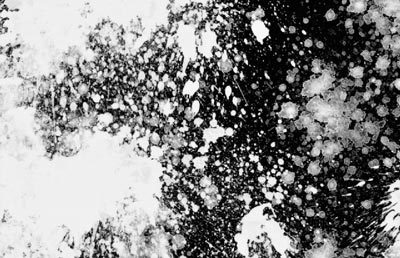
編集部の床の上に鮮血が小山のように盛り上がっていた。
朝、10時を少し過ぎた頃、やくざ風の2人組の男がずかずかと入って来て、アルバイトの女の子に、「編集長はいるか?」と聞いた。
「まだ出社していません」といおうとすると、奥にいた副編集長の大橋俊夫が、「何のご用でしょうか」と立ち上がり、男たちのほうに歩み始めた。
いきなり2人は特殊警棒を一振りすると、大橋に殴りかかった。大橋が床に崩れたのを見ると、あわてもせず部屋を出ていった。時間にして数十秒の出来事だった。
同じ時間に私は、浜松から東京行きの新幹線に乗っていた。平成3年8月13日であった。
昨夜は、第一勧業銀行の浜松支店長&歌手の小椋佳と食事をし、小椋の行きつけのクラブで彼とカラオケを一緒に歌った。
フライデーで彼について記事にし、一勧の広報にいた人間(後の作家の江上剛)から、小椋が会いたいといっているので、浜松までご足労願えないかと声がかかったのだ。
ちょうど合併後の休みだからと気軽に引き受けた。翌日は、小椋の奥さんも交えてゴルフをしようということになっていた。
翌朝起きると、なんだか胸騒ぎがする。小椋には、申し訳ないが急用ができたといって、新幹線に飛び乗った。
当時は携帯電話もあったが、大きくて重くて、とても持ち歩ける代物ではなかった。普段の連絡はポケベルだったが、東京、横浜を過ぎると電波は届きにくかった。
東京が近付いてくるとポケベルが鳴りだした。だが、電話を掛けに行くのが面倒で、そのままにしておいた。切ってもまた掛かってくる。番号はフライデー編集部。尋常でないことが伝わってくる。
東京駅で赤電話を見つけ、編集部に掛ける。編集次長の鈴木哲が出るなり、「やられました」。私もすぐに、「誰がやられた」。「大橋さんです。2人組に頭を殴られて、救急車で病院へ運びました」と哲。

すぐに戻ると告げて、タクシーに乗る。思い当たるのは、フライデーでやった山口組批判の記事だ。
「お前のところは、こんな記事を出して無事ですむと思うな」
脅しの電話は何本かあったが、合併号で1週間ほど編集部には人がいなくなる。時間が過ぎれば、奴らも忘れるだろう。そんな甘い気持ちが頭の片隅にあったのは間違いない。
編集部に殴り込んでくるとは想像もしていなかった。たけし事件のような素人集団とは違って、山口組のプロの鉄砲玉に違いない。大橋副編集長にもしものことがあったら、深刻な後遺症が残ったら、どう償えばいいのだろう。クーラーの利いたタクシーの中なのに、冷や汗が全身から滲み出てきた。
大橋は写真部からの出向という形でフライデーに来てもらっていた。私より年長で、温厚な人柄だから、編集部の人間たちの人望は厚かった。
編集部に駆け込むと、大量の血痕が目に飛び込んできた。その量は半端ではない。傷の深刻さを思い知らされた。
社の隣は大塚警察である。署員と警視庁からの人間たちが、あわただしく編集部中を動き回り、指紋などを採取している。
年かさの人間が、「編集長、後で話を聞かせてください」という。この事件のことはすぐにテレビで報じられていた。記者たちが取材させろといってくるが、すべては広報室に任せて、ハイヤーで大橋の入院している病院へ向かう。
どこの病院だったのか、記憶にない。すぐに病室へ行く。
私は物事を考える時、最悪の事態を想定して、どう対処すべきかを真っ先に考える。
たとえば、この記事を掲載したら、相手はどういう反撃をしてくるのか。出すと知った時点ですぐに出版差し止めをかけてくるのか。
出した後、民事と刑事両方で名誉棄損で訴えてくるのか。出版差し止めが認められる可能性はどれぐらいあるのか。名誉棄損で負けたら、いくらぐらいの賠償額になるのか。すべてをシミュレーションしてから決断を下す。
編集長在任中、「強気一点張り」「向こう見ず」などと評されたが、本当は、小心でいつも心の中では冷や汗を流していた。
病院へ着き、病室に入るなりベッドを見た。大橋副編集長はベッドから起き上がり、奥さんと話をしていた。体から力が抜け、その場に崩れ落ちそうになった。
大橋と奥さんにお詫びをし、容態を訊ねた。比較的明るい声で大橋が、
「一発殴られたとき、もうダメだと思って、前屈みにしゃがみこんだのがよかったようだ。後頭部を何発も殴られたが、血が噴き出たため、内出血せずにすんだことが幸いしたと医者がいっていた」
カメラマンとして多くの修羅場をくぐってきたベテランの知恵であった。
奥さんに、「ご主人をこんな目に遭わせてしまって申し訳ない」と深く詫びて、社へ戻った。
編集部員たちに大橋の容態を伝えた。「よかった」と安堵の声があちこちから聞こえた。
事件が報じられた後、私が最初に受けた電話は、安部譲二からだった。『塀の中の懲りない面々』を書いて売れっ子になった元暴力団員&作家は、さすがに人生の機微の分かる人だった。嬉しかった。
警視庁の人間から事情聴取された。「心当たりは?」といわれ、「これは推測ですが、たぶん、7月31日号でやった、ジャーナリスト溝口敦の『追いつめられた“最強軍団”山口組の「壊滅前夜」』という記事や、山口組幹部の姐さんが、新神戸の駅前にブティックを開き、下の者たちは余計な出費を迫られて迷惑しているなど、一連の山口組批判の記事がきっかけになったと思う」と答えた。
警視庁の人間は、「それなら凶器はすぐ見つかるだろう。彼らは、山口組に盾をつくと、こういう目に遭うという“脅し”が目的だから」といった。
その通り、翌日、講談社の裏手から特殊警棒が見つかり、指紋も検出された。警視庁捜査四課と大塚警察は、検出された指紋から、大阪府内に事務所がある山口組系暴力団の2人を割り出し、全国に指名手配した。
その数日後、2人は警視庁に出頭してきた。「すでに組を破門された」という破門状の写しを持参していた。
捜査員たちの調べで、犯人たちは、フライデー編集部を探しながら、社長室を覗いていたことが判明した。社長はいなかったが、もし在室していたらと思うとゾッとした。
この事件がきっかけで、講談社の警備体制が強化された。プロの警備員を雇って入り口に配備し、防犯カメラがあちこちに設置された。
それまでは誰でも自由に出入りできる緩さが講談社のよさだったが、社員はもちろん、外部の人間も受付で入館証をもらわなければ、社内に入れなくなってしまったのは、私のやったこととはいえ、痛恨の極みであった。
大橋副編集長のケガの回復は予想外に早く、1カ月後には仕事に復帰できた。
1年前は「幸福の科学事件」で世を騒がせ、翌年の同じ時期に「山口組鉄砲玉襲撃事件」が起きた。
ニュースを報じる側がニュースになったのは褒められたことではない。だが、フライデーという雑誌は、そうしたことも含めて丸ごとスキャンダラスな媒体である。
「平時に乱を起こす」。私の雑誌作りはそれに尽きる。常に話題を提供し続けながら第二期黄金時代を迎えようとしていた。
フライデーの売り物の一つはSEXYグラビアである。当時はヘアの写っているグラビアはご法度だったが、写真集や映画には変化が現れてきていた。
編集長就任早々、マリリン・モンローが自らバツ印をつけ、封印したヌード写真を掲載した。露出度はそう高くはないが、写真を一目見た時、やってみたいと思った。
だが、集英社が新雑誌を出す計画をしていた。その創刊号で、この写真を使いたいというオファーがあったと、エージェントから連絡があった。
そうなれば、こっちも引き下がれない。エージェントに間に入ってもらって、電話でオークションをやろうと申し出た。先方もOKだという。
最初は300万円ぐらいから始めたと記憶している。エージェントが向こうへ伝える。すぐに400万円出すといっていると電話が入る。
あっという間に1,000万円を超えた。そこで私は、局長と役員に、「この写真はどうしても手に入れたい。だが、このままいくと1,500万円ぐらいまでいくかもしれない」と報告し、許可を得た。
結局、こちらが1,600万円という金額を提示し、長い待ち時間の末、「先方が下りるといっています」と連絡があった。
モンローの写真を表紙とグラビア特集で使った。売り上げは5~6%程度伸びたようだから、帳尻はトントンというところだろうか。
このことがあってから、エージェントから、「フライデーは高く買ってくれる」と評判になり、これはという写真は、最初に見せてくれるようになったことが雑誌にとっての収穫だった。
そして平成4年10月、世界中を騒然とさせた歌手・マドンナの写真集「SEX」がフライデーに掲載されるのである。
(文中敬称略=続く)
<プロフィール>
元木 昌彦(もとき・まさひこ)
ジャーナリスト
1945年生まれ。講談社で『フライデー』『週刊現代』『Web現代』の編集長を歴任。講談社を定年後に市民メディア『オーマイニュース』編集長・社長。
現在は『インターネット報道協会』代表理事。元上智大学、明治学院大学、大正大学などで非常勤講師。
主な著書に『編集者の学校』(講談社編著)『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)『現代の“見えざる手”』(人間の科学社新社)などがある。連載
□J-CASTの元木昌彦の深読み週刊誌
□プレジデント・オンライン
□『エルネオス』メディアを考える旅
□『マガジンX』元木昌彦の一刀両断
□日刊サイゾー「元木昌彦の『週刊誌スクープ大賞』」
【平成挽歌―いち雑誌編集者の懺悔録】の記事一覧
・「平成挽歌―いち編集者の懺悔録」(9)(2019年07月02日)
・平成挽歌―いち雑誌編集者の懺悔録(8)(2019年06月25日)
・平成挽歌―いち雑誌編集者の懺悔録(7)(2019年06月18日)
・平成挽歌―いち雑誌編集者の懺悔録(6)(2019年06月11日)
・平成挽歌―いち雑誌編集者の懺悔録(5)(2019年06月04日)
・平成挽歌―いち雑誌編集者の懺悔録(4)(2019年05月29日)
・平成挽歌―いち雑誌編集者の懺悔録(3)(2019年05月21日)
・平成挽歌―いち雑誌編集者の懺悔録(2)(2019年05月14日)
・平成挽歌―いち雑誌編集者の懺悔録(1)(2019年05月07日)





























