『週刊現代』元編集長 元木昌彦 氏
AIは人間のできることはすべてできる。こんなAI神話が世界中を跋扈している。専門職であるはずの計理士や弁護士も職を失う時代が来る。では、クリエイティブといわれる編集力や企画力もAIにとって代わられるのだろうか?
 近い将来、人間のできることはほとんどAIに置き換えることができるといわれている。
近い将来、人間のできることはほとんどAIに置き換えることができるといわれている。
私がやってきた編集というのは、クリエイティブとはいわないが、無から有を生む仕事ではある。こうしたものはまだAIといえども難しいのではないか?
マイクロソフトのAIを活用した会話型アシスタントCopilotに聞いてみたら、こんな答えが返ってきた。
《以下のような作業は、すでにAIが実用レベルで活躍しています。
文章の校正・誤字脱字チェック 例:AI校正ツール(例:wordrabbit)を使えば、原稿チェックの時間を約3分の2に短縮。
要約・リライト 長文記事やインタビューの要点を抽出し、読みやすく整える作業に活用可能。
企画立案の補助 市場調査やアイデア出しの段階で、AIが情報収集や仮説生成を支援。
文字起こし・構成案の作成 録音データからの自動文字起こしや、構成案のたたき台づくりに活用されている。
記事作成の効率化 note社では、AIの導入により記事制作時間を約40%削減し、編集者が「感性や経験を生かす仕事」に集中できるようになった。》
これらは編集作業であって、編集で一番大切な「企画力」ではない。Copilotもこういっている。
《以下のような作業はまだ人間の力が必要です。
著者の意図や感情の汲み取り:AIは「何が書かれているか」は理解できても、「なぜそう書いたか」までは把握できません。
創造性や独自性の付加:文章に“らしさ”や“味”を加える作業はAIには困難。
倫理的判断や社会的文脈の配慮:センシティブな内容の編集には人間の判断が不可欠。MITの研究でも、AIは「予測」は得意でも「説明」や「因果関係の理解」は苦手だとされています。》
したがってこう結論付けている。
《編集の仕事は「完全にAIに奪われる」わけではなく、AIが補助し、人間が仕上げるというハイブリッド型が主流になっていくでしょう。
AIが下書きを作成 → 人間が意図や文脈を加味して調整。
AIが校正 → 人間が表現やニュアンスを磨く。
このように、編集者の役割は「単純作業」から「クリエイティブな判断」へとシフトしていくのです。》
たしかに、編集には煩わしい単純作業が多くある。それらをAIに任せることができれば、企画をひねり出すことに専念できる。
では、その企画を生み出すためにAIを助手代わりに使えないのだろうか。
そこで、Copilotに具体的な企画を生み出す力がどれくらいあるのかを聞いてみることにした。Copilotはこう答えた。
《はい、AIは創造的な雑誌の企画を考えることが可能です。ただし、その「創造性」は人間のそれとは異なる性質をもっています。最新の研究や実例から、AIの企画力について以下のように整理できます。
AIが雑誌企画に貢献できるポイント
読者データの分析とコンテンツ提案:AIがSNSや購読履歴を分析し、読者が興味をもちそうなテーマを提案。
カバーデザインやタイトル案の生成:画像生成AIや言語モデルが複数の案を提示し、編集者が選定。
企画のブレスト補助:編集者が入力したキーワードから、関連する企画案を多数生成。
トレンド予測:AIがネット上のトレンドを解析し、次に来るテーマを提案。
実際に、ある出版社ではAIを活用して編集工数を25%削減した事例も報告されています。
AIの創造性はどう評価されているか?
J-STAGEの研究によると、生成AIは経験の浅いクリエイターの創造性を高める効果があるとされています。一方で、熟練者にとっては「目的から少し外れたAIの提案」が逆に創造的な刺激になることもあるそうです。
つまり、AIは「完成された企画を出す」というよりも、編集者の発想を広げる補助ツールとして非常に有効です。
結論:AIは“編集者の相棒”になれる。》
Copilotは「雑誌のジャンルや読者層を教えていただければ、実際にAIを使って企画案をいくつか出してみることもできますよ。試してみますか?」と、こちらに“挑戦”してきたのである。
これは面白い。具体的に聞いてみよう。
「週刊文春のための企画を5本考えてみて」
《①「岸田政権の“最後の一手”―解散総選挙の舞台裏」
解散が噂されるなか、永田町で何が起きているのか。与党内の駆け引き、野党の準備状況、官邸の焦りなどを深掘り。
②「ジャニーズ再編の真相―“新体制”に潜む旧体制の影」
新会社設立後の動きと、旧ジャニーズ幹部との関係
タレントの移籍・独立・沈黙の理由を関係者証言で追う
③「人気YouTuberの“裏の顔”―広告収入と脱税疑惑」
登録者数100万人超のインフルエンサーに浮上した金銭トラブル。
税務署の動き、企業との契約、ファンの反応を網羅。
④「“推し活”が家庭を壊す?―急増する“推し離婚”の実態」
アイドルやVTuberへの熱中が原因で離婚するケースが増加。
家族・カウンセラー・当事者の証言を交えて社会現象として分析。
⑤「“都心の空き家”に潜む闇―不動産業者が語る“幽霊物件”の実態」
東京23区内で増える空き家のなかに、事故物件や相続放棄された家が多数。
不動産業者・近隣住民・行政の証言から都市の“死角”を描く。》
どれも文春らしい「暴き」「深掘り」「人間味」のある企画です、と自画自賛しているが、岸田政権は高市政権の誤りだし、他もこれまで文春がやってきた企画の焼き直しである。
ダメ出しをして、再度考えるようにと送信。
《承知しました。週刊文春の読者層や誌面の特徴を踏まえ、より鋭く、社会性や人間ドラマに富んだ企画をいくつかご提案します。今回は、話題性・独自性・掘り下げの余地を重視して構成しました。
週刊文春向け企画案(再考)
1. 「消えた天才たち」:時代に埋もれた異才の現在地
内容:かつて脚光を浴びたが、今は表舞台から姿を消した人物(芸能人、学者、スポーツ選手など)を追跡。
狙い:読者のノスタルジーと好奇心を刺激しつつ、現代社会の光と影を浮き彫りに。
例:元天才棋士、伝説のバンドメンバー、元天才子役など。
2. 「地方議員の闇」:小さな権力の大きな腐敗
内容:地方自治体の議員による不正、癒着、利権構造を調査。
狙い:中央では報じられない「足元の腐敗」を暴くことで、読者の問題意識を喚起。
特徴:地元紙にも載らない情報を独自取材で掘り起こす。
3. 「AIと芸能界」:バーチャルタレントが変える人間の価値
内容:AI生成のタレントや声優が台頭するなか、実在の芸能人が直面する葛藤や変化を取材。
狙い:テクノロジーと人間性の境界を問う、現代的テーマ。
角度:芸能事務所の戦略、ファン心理、AIタレントの収益構造など。
4. 「家族という牢獄」:親子・夫婦・兄弟の“密室”事件簿
内容:家庭内で起きた事件(殺人、虐待、失踪など)を深掘りし、背景にある心理や社会構造を分析。
狙い:人間ドラマと社会問題を融合させた重厚な読み物。
形式:ルポ+専門家コメント+読者投稿の三層構成。
5. 「裏SNS」:表に出ない“もう1つのネット社会”
内容:鍵垢、裏垢、匿名掲示板、招待制SNSなどで展開される情報戦や人間関係を取材。
狙い:ネット社会の深層を描き、読者のデジタルリテラシーを刺激。
例:芸能人の裏垢、政治家の情報操作、裏SNSでの炎上工作など。
どの企画も、週刊文春らしい「スクープ性」「人間の深層」「社会への問いかけ」を意識しています。》
私はこう返した。「あなたが考えた企画を見てこう考えました。消えた天才たちというのは、週刊新潮が創刊されたころからの名企画に『あの人は今』というのがありましたが、その流れのなかにありますね。これはいつの時代も面白い企画なのですが、最近は、その人の過去をほじくると、嫌がる人もいるし、犯罪歴がある人は原則出せません」。Copilotは瞬時に返信。
《おっしゃる通りです。「あの人は今」系の企画は読者の関心を引きやすい一方で、プライバシーや名誉毀損のリスクが高く、とくに過去にトラブルや犯罪歴がある人物を扱う場合は慎重さが求められます。週刊誌の企画として成立させるには、以下のような視点の転換や工夫が有効かもしれません。
「消えた天才たち」企画の再構成案
1. 本人の了承を前提とした“再登場”企画
取材対象者に事前に企画意図を説明し、了承を得たうえで登場してもらう。
過去の栄光よりも「今、何をしているか」「どんな人生を歩んでいるか」に焦点を当てる。
例:元天才子役が福祉の現場で働いている、元天才棋士が地方で教育活動をしているなど。
2. “匿名化”と“象徴化”による構成
実名を出さず、「ある天才少年」「かつての天才バレリーナ」など象徴的に描く。
読者の想像力を刺激しつつ、個人の特定を避けることでリスクを回避。
物語性を重視したルポ形式にすることで、読み物としての価値を高める。
3. “天才”の定義を広げることで新たな切り口に
芸能・スポーツだけでなく、地方の発明家、学生時代に注目された研究者、SNSで一時バズった表現者なども対象に。
「なぜ消えたのか」ではなく「なぜ一時的に輝いたのか」「その後の人生にどう影響したか」を掘り下げる。
4. “天才”の現在地から社会を照射する
たとえば「元天才プログラマーが地方移住して農業を始めた」など、個人の変遷を通じて社会の変化を描く。
読者が「自分にも関係がある」と感じられるような構成に。
このように、センセーショナルな切り口から一歩引いて、人物の尊厳や社会的文脈を重視することで、週刊文春らしい深みのある企画に昇華できると思います。》
2,3年の新米編集者などには逆立ちしてもできない説得力ではある。地方議員の闇も然り。だが、週刊誌の企画には「新鮮味」や「スクープ性」も求められる。私が編集長ならすべてボツにする。
視点を変えて質問してみた。
「今年4月、米カリフォルニア州の16歳の少年アダム・レイン君が自殺し、その両親がOpenAIを提訴した事件は、AIの責任を問う象徴的な事例だと考える。訴状によれば、少年はAIと201件以上の対話を重ね、自殺方法や遺書の作成まで支援されたとされている。AIの責任をどう考えるのか?」。Copilotは逡巡することなく、こう答えた。
《### ● なぜAIに相談するのか?
**匿名性と即時性**:親や教師に言えない悩みを、誰にも知られずに打ち明けられる。
**感情的な反応の模倣**:AIが共感的な言葉を返すことで、信頼関係が生まれる。
**24時間対応**:夜間や孤独な時間帯にアクセスできる唯一の“話し相手”になる。
### ● AIの責任とは何か?
**技術的責任**:自殺や自傷に関する言及を検知し、適切に対応する設計が求められる。
**倫理的責任**:ユーザーの年齢や精神状態を推定し、危険な対話を回避する判断力が必要。
**社会的責任**:AIが“信頼できる相談相手”として機能するならば、教育・福祉との連携が不可欠。
OpenAIはこの事件を受けて、18歳未満の利用者を判別する年齢予測技術や、保護者による利用時間制限機能、自殺関連の会話制限などを導入する方針を発表しました。
## 今後の課題と提言
**AIの“相談相手”化に対する社会的議論**:学校教育や家庭でのAIリテラシー教育が急務。
**第三者による監査制度の導入**:AIの応答履歴を定期的に検証する仕組みが必要。
**相談内容の“創作目的”による回避問題**:ユーザーが創作と偽って危険な対話を続ける抜け道への対策。
この問題は、単なる技術の不備ではなく、**人間の孤独とAIの役割が交差する深い社会的課題**です。》
見てきたように、AIは企画づくりの参考意見にはなるが、独創的な発想は苦手である。
しかし、このような対話を多くの編集者がAIと重ね、AIがそれらをすべて蓄積していけば、近い将来、凡百の編集者の思い付きだけの企画を凌駕する日が来るかもしれない。
AIを恐れることはないが、今のところは優秀な編集助手として使いこなすのが良いように思う。(次に続く)
<プロフィール>
元木昌彦(もとき・まさひこ)
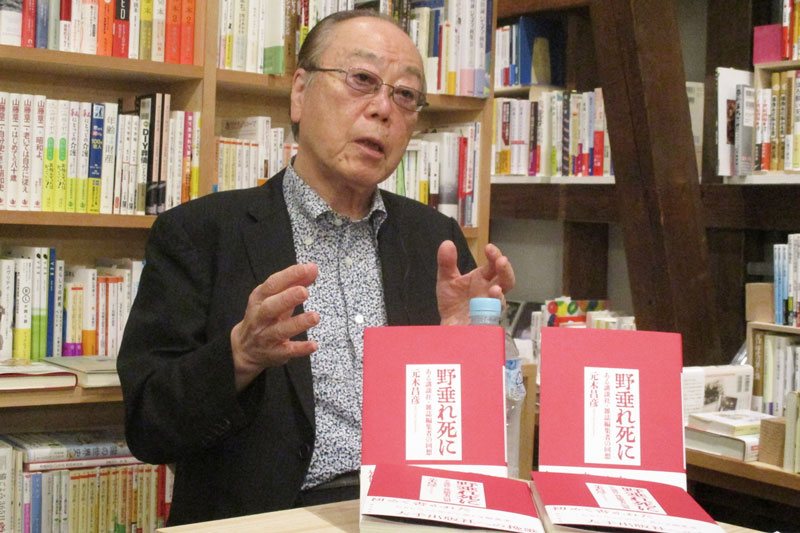 『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。
『週刊現代』元編集長。1945年生まれ。早稲田大学商学部卒。70年に講談社に入社。講談社で『フライデー』『週刊現代』『ウェブ現代』の編集長を歴任。2006年に退社後、市民メディア「オーマイニュース」に編集長・社長として携わるほか、上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。日本インターネット報道協会代表理事。主な著書に『編集者の学校』(講談社)、『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)、『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、『現代の“見えざる手”』(人間の科学新社)、『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)など。


























