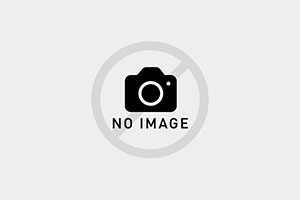【クローズアップ】育児介護休業法改正が問う企業の真価 進む制度整備、問われる実効性
2025年10月、改正育児・介護休業法が完全施行された。法律は整えられ、中小企業を含む全ての事業者に対応が求められるが、実際の現場では運用格差の広がりが懸念される。たとえ社内的に制度を整えても、「整えただけ」と「機能している」ことの間には大きな隔たりがある。形骸化を防ぐには、職場文化そのものを変える視点が欠かせない。柔軟な働き方や相互理解を軸に成果を上げる企業も現れ始めた。改正は単なる法対応にとどまらず、働き方改革の新たなフェーズを象徴する転換点となっている。
進む制度の整備
現場の差は埋まるのか
2025年10月から改正育児・介護休業制度が完全施行となった。今回の改正により、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるよう、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職を防ぐための制度整備が大きく進んだ。誰もがそれぞれの希望に応じて仕事と家庭を両立できる環境づくりは、少子高齢化が進む日本社会において避けて通れない課題であり、企業の取り組みも新たな段階を迎えている。
しかし、現場に目を向けると、制度の定着度には明確な差がある。法律上の整備を終えても実際の取得率や運用状況が伸び悩む企業がある一方で、柔軟な働き方や相互理解を軸に成果を上げる企業も現れている。女性活躍推進や働き方改革の流れのなかで、改正制度を起点に職場の在り方そのものを問い直す動きが始まっている。
改正育児・介護休業法施行
中小企業も例外なし
 1991年に制定された育児・介護休業法は、少子高齢化の進行を背景に、男女がともに仕事と家庭を両立できる社会の実現を目的として段階的に改正が進められてきた。今回の改正は25年4月と10月にかけて段階的に施行された。
1991年に制定された育児・介護休業法は、少子高齢化の進行を背景に、男女がともに仕事と家庭を両立できる社会の実現を目的として段階的に改正が進められてきた。今回の改正は25年4月と10月にかけて段階的に施行された。
25年4月施行分では、育児と介護の両面で見直しが行われた。育児では、子の看護休暇の対象年齢が「小学校第3学年修了まで」に拡大され、感染症による学級閉鎖や入園・卒園行事も取得事由に追加。所定外労働の制限(残業免除)の対象も小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大された。育児休業取得状況の公表義務は、従業員1,001人以上から301人以上の企業に拡大。介護分野では、介護離職防止のための雇用環境整備や個別の周知・意向確認などが義務化され、介護休暇を取得できる要件に、継続雇用期間6カ月未満の労働者も含まれることとなった。さらに、育児期や介護のためのテレワークの導入が努力義務化され、短時間勤務制度の代替措置としても認められるようになった。
10月施行分では、3歳から小学校就学前の子を持つ労働者に対し、事業主がフレックスタイム、テレワーク、養育両立支援休暇の付与など5つの措置から2つ以上を選択して導入することが義務づけられる。さらに、妊娠・出産時や子が3歳になる前の段階で、労働者の意向を個別に聴取し、勤務条件に反映することも求められる。
これらの改正は、育児休業取得状況の公表義務適用拡大を除き、全企業が対象となる。同時に、制度の変化を契機として、自社の働き方や人材活用の在り方を再点検する良いタイミングとなっている。
利用者数増加も
数字が示す格差
育児・介護休業法は1991年の制定以来、男女ともに育児休業の取得が可能となっているが、長年にわたり実態面では男女格差が続いてきた。近年ようやく、男性の育児休業取得率は大きく伸びつつある。厚生労働省の調査によると、24年度の男性育休取得率は40.5%と初めて40%を超え、前年の30.1%から10.4ポイント上昇した。女性の取得率(86.6%)とは依然差があるものの、取得が例外ではなくなりつつあることを示している。一方、23年度に全国の従業員1,000人超のすべての企業・団体を対象に行われた調査によると、男性の育休など取得率は46.2%と高い水準に達したが、平均取得日数は46.5日。取得率が高い企業ほど期間が短くなる傾向も見られた。
一方で、介護をしながら働く人の数も急増している。22年には15歳以上の人で介護をしている人は約629万人で、そのうち58.0%が有業となっている。高齢化の進行により、今後は「介護離職の防止」が重要課題となる。仕事と介護の両立を支援するためには、休業制度だけでなく、テレワークや時差勤務など柔軟な働き方の選択肢を拡充する必要がある。22年度に厚生労働省委託事業として行われたアンケート調査によると、子育て世代の働き方に関する調査では、正社員の女性は子が2歳を過ぎるころから「短時間勤務」や「残業のない働き方」を希望する割合が増える。男性でも、子の年齢にかかわらず約4~5割が柔軟な働き方を望んでおり、性別を問わず“時間と場所に縛られない働き方”へのニーズが高まっている。
成果を上げる企業
制度を“文化”に変えていく
改正育児・介護休業制度の完全施行を目前に、制度を整備するだけで終わる企業と、実際に成果へと結びつけている企業との違いが明確になりつつある。福岡県女性の活躍推進ポータルサイトに先進的な事例として紹介されている(株)エッジコネクション(東京都品川区)は、成果を上げている企業の1つである。同社では女性社員の比率が高く、とりわけコールセンター部門では子育て世代の女性が中心を担っている。自然発生的に「女性が活躍しやすい職場」が形成された背景には、ライフステージの変化を前提にした仕組みづくりがあった。

女性が働く様子
同社は17年ごろから、子育て世代が安心して長く働けるように制度を整備してきた。復職支援金として、育休からの復帰後に10万円を支給する「復職祝金制度」を導入。支給は復職3カ月後とし、早期離職を防ぐ工夫を施した。育休・産休の取得率と復帰率はいずれも100%を維持し、コールセンター業界の平均離職率が30%といわれるなか、同社は2%前後という極めて低い水準を実現している。また、時短勤務でも管理職としてキャリアを継続できる制度を整え、復職後もキャリアを途絶えさせない仕組みを築いた。
さらに、社員同士の相互支援を促進するために、給与とは別に設けられた報酬制度を利用して、同社では「休むと迷惑をかける」「申し訳ない」といった心理的負担を軽減するために、休業中の業務を他の社員が引き受けると、通常業務の1.3倍に相当するインセンティブ報酬が支給される「カバーインセンティブ制度」を設けている。単なる善意に頼らず、報酬のかたちで貢献を評価する仕組みである。この報酬は制度内で処理され、休んだ社員が発注者として原資を負担するかたちをとっており、これにより「お互い様」という文化と経済的公平性が両立している。これにより、休む側も気兼ねなく、カバーする側も納得感をもって働ける環境が形成された。
同社の経営理念には「感情ではなく仕組みで解決する」という考え方が貫かれている。善意や思いやりは個人差があり、期待に依存すれば不公平感を生みやすい。すべての仕事に対して報酬基準を明確に設定し、社員は自らの成果に応じて評価を受ける。給与は上司の主観ではなく成果で決まり、努力した分だけ報われる構造が整っている。こうした透明性の高い評価制度が、女性に限らず社員全体の意欲向上と公平な競争環境を支えている。
経営層にも女性が多く、取締役や執行役員、部長職に女性が就いていることも象徴的である。創業期からこの仕組みを確立してきた大村康雄代表は「誰もが自分らしく働ける職場を目指してきた結果、自然とD&Iが進んだ」と語る。感情論ではなく制度と設計によって働きやすさを実現する姿勢が、結果として高い定着率と組織の安定をもたらした。
一方、法改正を受けて育児・介護休業制度を就業規則に明記するだけで運用実績がともなわない例も少なくない。代替要員の確保が難しい、繁忙期に取得できない、周囲の理解が得られないといった構造的問題が制度の定着を妨げている。エッジコネクションのように「整備から運用へ」、そして「制度から文化へ」と昇華させるには、働き方改革を自社戦略の一部として位置づけ、現場の声を取り込むことが欠かせない。
高齢化が進むなか
迫る介護離職の現実
高齢化の進展により、家族の介護を担いながら働く人は急増している。こうしたなか、介護を理由に離職する「介護離職」は深刻な社会課題となっており、その防止は喫緊のテーマとなっている。介護休業制度の規定がある事業所の割合は、24年時点で事業所規模5人以上では72.3%となっているものの、労働者に占める介護休業利用者割合は依然として0.1%と低水準である。制度を知らない、あるいは利用をためらう労働者が多いことがうかがえる。こうした状況を踏まえ、25年4月施行の法改正では、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和や個別の周知・意向確認等の義務化が盛り込まれた。
制度の枠組みは充実しつつあるが、「介護を理由に休みづらい」という雰囲気が根強く残る企業も少なくない。介護は突発的かつ長期化しやすく、業務の属人化が進む中小企業ほど代替要員の確保が難しい。制度を設けても運用に至らず、結果的に介護離職が発生してしまう。
今後は、介護支援を個人の福利厚生ではなく、企業のリスクマネジメントとして位置づける視点が求められる。仕事と介護の両立支援を実効性ある制度として定着させることが、長く働くことができる雇用環境の構築に直結する。24年の離職率は14.2%で、そのうち0.2%が介護・看護を理由としている。高齢化が進むなかで、介護をしながら働く人の割合は増加していくことが予想される。育児とならび、介護を支える仕組みの拡充こそが、これからの働き方改革の核心である。
立場で異なる温度感
互いに納得できる運用を
 改正育児・介護休業制度の完全施行に合わせ、企業は制度を整え、それを実際に運用しながら、自社の実情に即した「支援のかたち」を模索していく必要がある。その際に求められるのは、制度を整備したことで満足することではなく、運用のなかで浮かび上がる課題を可視化し、改善を重ねて職場環境を成熟させていこうとする継続的な姿勢だ。
改正育児・介護休業制度の完全施行に合わせ、企業は制度を整え、それを実際に運用しながら、自社の実情に即した「支援のかたち」を模索していく必要がある。その際に求められるのは、制度を整備したことで満足することではなく、運用のなかで浮かび上がる課題を可視化し、改善を重ねて職場環境を成熟させていこうとする継続的な姿勢だ。
現場では「周囲に迷惑をかけたくない」「評価に影響するのでは」といった遠慮や同調圧力が生まれやすい。さらに、子育て世代、介護世代、独身層といった立場の違いによって、制度への関心や必要性には温度差があり、この意識の非対称性が制度定着の大きな障壁となっている。こうした環境のなかで、休業制度を当たり前に利用できる職場文化を根づかせるためには、休む側に罪悪感を生ませず、カバーする側にも不満を抱かせない、公平で透明な仕組みづくりが欠かせない。その要となるのが、経営層の明確なリーダーシップと、現場での相互理解の深化である。
一方で、先述したエッジコネクションのように、中小企業のなかからも実践的なモデルが生まれつつある。感情や慣習に依存しない制度設計を通じて、育児や介護と仕事の両立を“特別なことではなく当然のこと”として受け入れる文化をかたちづくる試みである。こうした実践が広がれば、法改正は単なる義務対応ではなく、働く人すべてが支え合いながら力を発揮できる社会への転換点となる。改正育児・介護休業制度の完全施行は、制度を文化へと昇華させるための出発点であり、その成否は、現場における理解と信頼の積み重ねにかかっている。
【岩本願】