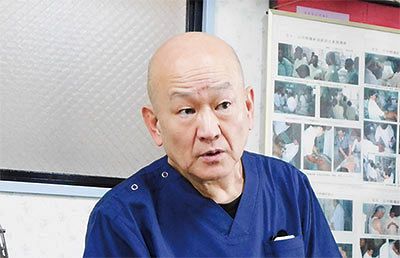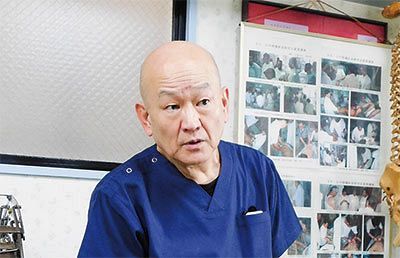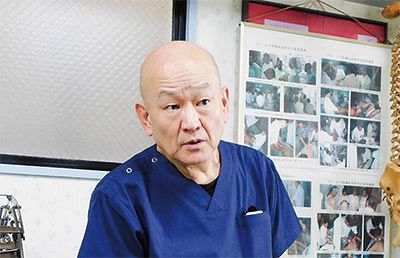ヘルスケア業界のニュースや、ヘルスケア業界に関する消費者庁、厚生労働省、国民生活センター、消費者団体などのニュースを配信。
2019年11月20日 10:00
さて、「健康寿命」という言葉が広く行きわたってきております。この言葉は、介護保険制度(2000年)ができてから一躍有名になりました。日本人の平均寿命が世界でもトップクラスであるのは、ほとんどの日本人は知っていたのですが、実は他人による介護を必要としたもので、寝たきりで、ただ生きている時間(不健康な時間)が男性は9年間、女性は約12年間もあることがわかってきました。
2019年11月19日 16:50
未病の考え方を普及し、未病総研メソッドを提案する団体として、(一社)日本未病総合研究所=未病総研(代表理事:福生吉裕)が今年1月に発足した。(一社)日本医学会連合の高久史麿名誉会長、日本医師会の横倉義武会長両氏を顧問に迎え、企業・団体とコンソーシアムを組んで未病総研メソッドの振興に取り組んでいくという。福生代表理事に未病総研設立の目的と今後の事業展開について語ってもらった。
2019年11月16日 07:00
長尾院長はいつも朗らかに口ずさむ。「1日1日消えゆく毎日、健康で楽しく生きなければもったいない、もったいない」。1人ひとりの健康の重要さを説いてくれる。そして「1人でも多くの患者さんを健康にしたい!笑顔にしたい!」という自分の役割を具体的に語ってくれる。
2019年11月15日 07:00
筆者と長尾院長との出会いは2年前に遡る。仕事と家事との多忙な毎日のなかで、いつも風邪気味だったり、頭が痛かったりする不健康な状態に悩まされていた。そんなときに、河村勝美氏から長尾治療院を紹介してもらったのである。
2019年11月14日 10:37
100年の人生を生きることは当たり前になるのか――。「人生100年時代」が来るとすれば、生き方も働き方もこれまでと変わる。「100歳現役貫徹の秘訣」と題したこのコーナーでは、さまざまな人物やトピックを取り上げ、仕事を充実させ健康増進を図るためのヒントをお届けする。
2019年11月13日 10:25
予防医療・健康増進を実践する医療施設として、全国から年間延べ3万人以上が訪れる診療所として注目されているのが海風診療所。今回、院長・沼田光生氏に、同院が推進する、予防医療事業の内容について聞いてみた。
2019年11月7日 14:00
私は高校の学校医をしておりまして、主に若年層に薦めています。今の学生は活気がない、便秘や病気しがち、学力に関しても昔に比べると勉強に対する意欲が薄れ気味の人が多いですね。高麗人参が、そのすべてをサポートできるわけではありませんが
2019年11月1日 10:00
「薬と食べ物は元を質せば同じ」という意味の「医食同源」という言葉は、日本語由来の新しい言葉と言われ、中国では古来より、「飲食薬食同源」または「薬食同源」という言葉があります。中国では、医学の歴史が食事の歴史であるように、古代から食事学が発達してきました。
2019年10月31日 10:00
中医学の歴史は古く、BC770年『黄帝内経』や500年『神農本草経』まで遡ります。その後は中老師たちが独自に改善を行い、中国内それぞれの地域でローカル化して発展してきました。それを1949年に毛沢東によって「中国医学の統一化」が行われ、現在に至っています。
2019年10月30日 10:00
現代の医療技術の発展は目覚ましいものがあります。しかし、医学が進歩しても病気や患者数は減るどころか増える一方です。その根底には生活養生、生活環境の問題があります。人は誰でも病気にかかりたくありません。そのためには、病気になる原因や病気にならない方法を知ることが重要です。
2019年10月29日 16:06
2018年6月にWHO(世界保健機関)が定める「国際疾病分類」の第11回改訂版で「伝統医学」として初めて中医学(漢方)を始めとする東洋医学が第26章に入った。それはなぜか。日本でも今「人生100年時代」を迎え、「生活習慣病」などを中心に中医学の必要性が急速に叫ばれている。
2019年10月29日 10:37
予防医療・健康増進を実践する医療施設として、全国から年間延べ3万人以上が訪れる診療所として注目されているのが海風診療所。今回、院長・沼田光生氏に、同院が推進する、予防医療事業の内容について聞いてみた。
2019年10月26日 07:00
Cさんは長尾治療院で初めて治療を受けた時からすぐに効果を実感し、今では週1回のペースで通院している。本人にパーキンソン病であることの自覚はないが、針治療を受けると「体が軽くなり、動きやすい」ことを実感しており、実際に治療前と後ではCさんの歩き方が変わる。
2019年10月25日 09:00
60歳以上で100人に1人が発症するといわれるパーキンソン病は、脳内で運動の指令を伝えるドパミンが欠乏することで、運動機能に障害があらわれる進行性の疾患である。症状は体の片側から出始め、次第に反対側に広がり、ゆっくりと進行していく。現在の医療では原因は特定されておらず、ひとたび発症すると完治することはないが、鍼灸治療では疾患の進行を抑制することができる。
2019年10月24日 09:00
一般に健康住宅というと、バリアフリーや無垢材などの自然素材を使った住宅というイメージがあるが、これとはまったく違った視点から家づくりを行うのが、「100歳住宅®」を開発した(株)マツドットコムアイエヌジー(本社:愛知県豊明市、松本昇社長)だ。
2019年10月23日 16:18
「0次予防」という言葉をご存知だろうか。病気になったら治す治療医学に対し、1次予防(健康づくり)、2次予防(健診等での早期発見)、3次予防(重症化予防)という概念がある。「0次予防」は1次予防の一歩手前の概念で、病気のリスクを少しでも減らそうという超早期の予防アプローチといえる。今、住宅産業では「0次予防」として、住みながら健康になる「健康住宅」を開発・普及する動きが広まっている。
2019年10月23日 11:04
予防医療・健康増進を実践する医療施設として、全国から年間延べ3万人以上が訪れる診療所として注目されているのが海風診療所。今回、院長・沼田光生氏に、同院が推進する、予防医療事業の内容について聞いてみた。
2019年10月23日 07:00
確かに保健機能食品のなかでトクホ、機能性表示食品、そして栄養機能食品という3つの制度が共存しており、今回、トクホと機能性表示食品の棲み分けが大きな課題となっている。
2019年10月21日 07:00
18年6月15日に閣議決定された「統合イノベーション戦略」および「未来投資戦略2018」において、トクホ等の保健の用途に係る表示の拡大についてその可能性を検討することとされていた。